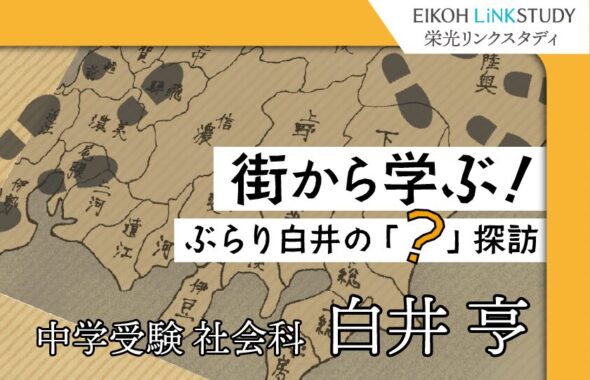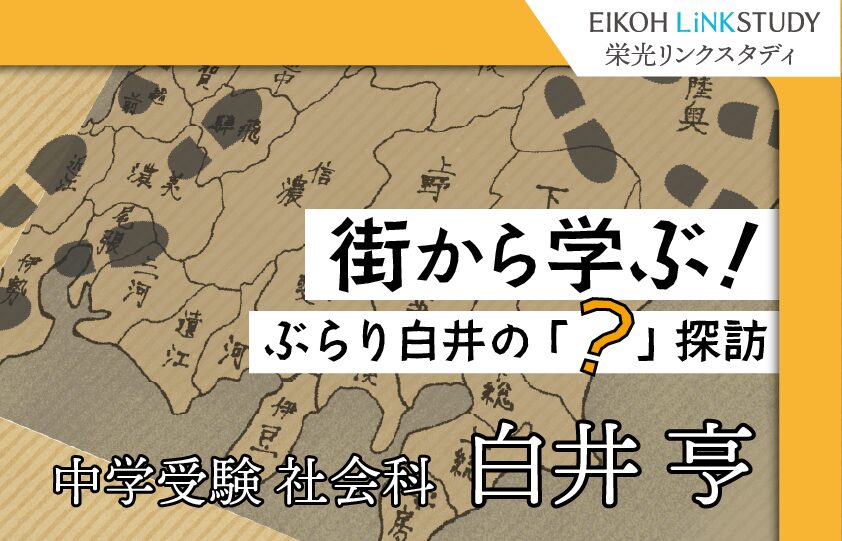
~三重県四日市市
工業都市のいろいろな顔編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
令和の日本では、人々の環境への関心も高くなっており、快適な居住環境が保たれるというのは当然の権利という認識になっています。しかし、昭和以前の日本では、環境を犠牲にしてでも経済を発展させようとした時期がありました。
1950年代の後半から1970年代の前半の日本は、高度経済成長期といわれる好景気が続いた時代でした。工業の著しい発展などを背景に、平均10%という高い経済成長率を続け、日本人のくらしはとても豊かになっていきました。しかし、その一方では日本各地で公害が発生し、なかでも特に被害の大きかった4つが「四大公害病」です。リンスタのテキストにも「1950年代後半から1970年代にかけて,日本各地では公害事件が多発しました。中でも,多くの公害病患者を出した,水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく・第二〔新潟〕水俣病を,四大公害病といいます。」というように説明されています。
今回は、その1つとなった三重県四日市市を訪ねてみることにしました。テキストに書いてある四日市市は、巨大な石油化学コンビナートのある工業都市のイメージが強くなっていますが、実際はどのような街なのでしょう。

まずは、地図で四日市市の場所を確かめてみましょう。 三重県北部にある四日市市は、県庁所在地の津市よりも人口が多く、県内で最大の都市になっています。地図中には名古屋駅の位置も入れましたが、比較的近いということがわかると思います。現在の四日市市は、石油化学工業を中心とした工業都市であるだけでなく、名古屋のベッドタウンという役割も担っているのです。名古屋駅から乗った近鉄線の急行電車は30分余りで四日市に到着しましたので、東京でいえば、横浜、千葉、さいたまあたりのイメージでしょう。時刻表を確認してみると、朝の四日市駅からは数多くの名古屋行き電車が出ています。下の写真を見ても、都会の駅という雰囲気ですよね。

まずは四日市ぜんそくについて学ぼうと、駅の近くにある環境未来館という施設に向かいました。同じ建物内には市立博物館もあり、四日市の歴史も学ぶことができました。どちらの施設も無料というのがありがたいですね。同じ建物内の2つの施設ですので、この後の表記はすべて博物館で統一しますね。
港があって街道が通っていた四日市は、古くから交通の要衝として栄えていました。室町時代には、4のつく日に定期市が開催されていたということが記録に残っており、それが四日市の地名の由来にもなっているそうです。また、江戸時代には東海道の43番目の宿場町となり、江戸と京都を往復する人々だけでなく、伊勢神宮への参拝客もここを通過していきました。「お蔭参り」とも呼ばれた伊勢神宮への旅は、江戸時代の庶民にとっての憧れでした。多いときには、年間数百万人の人が旅をしたといいますから、四日市の宿場町も賑わっていたのでしょうね。博物館には、市の様子や宿場町の様子を再現した展示もありました。
江戸時代は栄えていた四日市ですが、幕末に起こった大地震で発生した津波によって防波堤が破壊され、港の水深が浅くなったことで使い物にならなくなってしまいました。港と東海道が町の発展を支えていた四日市では、港の復興は必要不可欠なものでしたが、思うように計画が進みません。そんな四日市の大ピンチを救ったのが、稲葉三右衛門という商人でした。三右衛門は、自らの資材を投じて防波堤の建設をおこないました。JR四日市駅前には三右衛門の像が建てられており、四日市を代表する偉人であることがわかります。
今度は四日市ぜんそくについての展示を見に行きます。この日は、2階の常設展示に加え、4階で四日市ぜんそくに関する特別展示もあったので、より詳しく学ぶことができました。さまざまな資料の中には、当時の写真もあり、「公害マスク」をつけて登下校する子どもたちや、大勢の子どもが一斉にうがいをしている学校の様子などに目を奪われました。当時の学校では、日課表の中にうがいの時間が複数回あったようです。そんな劣悪な環境の中で多くの命も奪われました。特に強く印象に残ったのは、ぜんそくのために9歳で亡くなった女の子の話でした。未来への明るい希望を持ちながら幼くして奪われた命の理不尽さを思い、思わず涙がこぼれてきそうになりました。
さて、博物館をひと通り見学した後は、展示されていたものを参考に四日市の散策に向かいます。今回は目的地までの距離があるため、歩きではなく自転車を借りることにしました。近鉄四日市駅近くの駐輪場では、なんと120円という格安の価格で、自転車を1日レンタルできます。240円払うと電動自転車が借りられるので、もちろん私は電動を借りました。それでも驚きの安さですよね。借りるときには身分証明書を見せて利用証を作るのですが、おそらくこの利用証を再度使うことはないでしょうね(笑)

まず向かったのは、下の写真の旧東海道です。宿場町だった江戸時代の様子を見つけようと思ったのです。しかし、たどり着いた旧東海道は、昔の街道らしい面影はあるものの、宿場町らしい風景はあまり残されていないようです。この道は近鉄四日市駅のほうにも伸びているのですが、駅に近いところではアーケードになっていますので、さらに旧街道の雰囲気は少なくなっています。都市の規模が大きくなると昔の建物などを残すのは難しくなるでしょうから、しかたのないことなのかもしれません。でも、1つ歴史を感じるものを見つけましたよ。それは「創業1550年」という歴史ある和菓子屋さんです。ここの名物は餡の入った餅を薄く伸ばして焼いた〝なが餅〟というお菓子で、江戸時代にはお伊勢参りの旅人たちにも喜ばれていたようです。東海道や伊勢街道沿いにはこのような餅を販売する店が多くあるらしいのですが、ここ笹井屋さんはそのなかでも最も長い歴史を持っているのだそうです。せっかくなので、いちばん小さな7本入りのものを1つ購入してみました。ホテルに戻ってから食べてみたのですが、薄く焼かれた餅は香ばしくてとても食べやすく、あっというまに7本すべてを食べ切ってしまいました😋

しばらくすると雨がポツポツと落ちてきました。駅の近くにはアーケードの商店街があったので、とりあえずいったん戻って雨宿りをすることにしました。このときは「ついてないなぁ」と思ったのですが、この雨宿りの時間が思わぬ幸運に繋がるのです。 20分ほどで雨が上がったので、再び自転車に跨って工場地帯に向かいました。工業都市四日市らしい風景を見たいということもあったのですが、目的地としたのは2つの重要文化財です。
まず1つ目の重要文化財は、下の写真の末広橋梁です。写真には、橋の上に立つ鉄骨組の構造物と、そこから伸びるワイヤーが確認できると思います。列車が通っているので普通の橋に見えますが、通常時のこの橋は中央部が跳ね上がっていて船が通過できるようになっています。この末広橋梁は、国内では現役唯一の「跳開式可動鉄道橋梁」なのだそうです。 先ほどの幸運とはまさにこの写真の瞬間です。橋の姿を見られればいいと思っていたので、列車が通過する時間などはまったく調べていませんでした。しかし、橋の近くに行ってみたところ、カメラを持った親子連れがいたので、「もしかして列車が来るのでは?」と思い、しばらく待ってみることにしました。5分ほど待っていると踏切の鳴る音が聞こえ、貨物列車が橋を通過していきます。普通の橋に比べるとやっぱり不安定なんですかね。列車はゆっくり、ゆっくりと橋を渡っていきました。もし、雨宿りをしていなかったら、この風景を見ることはできなかったでしょうね。あとで調べてみたところ、列車が通過するのは1~2時間に1度程度らしいので、この写真を撮れたことは本当に幸運でした。ちなみに、この橋の南には臨港橋という道路橋があるのですが、こちらも船が通るときには跳ね上がる架道橋です。この橋の興味深いポイントは、入口に踏切が設置されていることでしょう。橋が上がっているときは踏切が閉じられて、通行できないようにするのだそうです。

さて、次に向かったのは稲葉翁記念公園です。稲葉翁とは、四日市の港を整備した稲葉三右衛門のことですね。ここには、三右衛門が築いた堤防のレプリカがあります。下の写真は、港の外側にあたる方向から撮ったものです。小さくてわかりにくいかもしれませんが、堤防の真ん中あたりに横に並ぶ複数の穴があるのがわかるでしょうか?

この堤防は〝潮吹き防波堤〟と呼ばれており、そのしくみは次のようになっているそうです。
まず、防波堤自体が手前側の低いものと奥側の高いものの二重構造になっています。港の外からやって来た波は、まず低いほうの防波堤により力を弱められます。それを越えた波は高いほうの防波堤に受け止められて、2つの防波堤の間に設けられた溝に流れ込み、〝潮吹き穴〟とよばれる穴から港の内側に流れ込むのだそうです。昔の防波堤は津波によって破壊されたわけですから、少しでも波の力を弱めようという工夫をしていることがよくわかりました。 この公園からは、海の向こう側に実際の潮吹き防波堤を見ることもできます。下の写真ではちょっとわかりにくいかもしれませんが、防波堤に横一列に並んだ穴が確認できました。こちらのほうは港の内側なので、防波堤は二重構造にはなっていません。外側にある二重構造の防波堤が受け止めた海水が、この穴から出てくるのですね。

工場地帯の見学を終え、近鉄四日市駅近くの駐輪場に自転車を返却し、次の目的地に向かうためにJRの四日市駅に向かいます。近鉄四日市駅とJR四日市駅の間は1㎞強の距離があり、歩くと15分ほどかかります。この道は四日市市のメインストリートなのですが、近鉄の駅から離れていくにしたがって次第に商店が少なくなり、ほぼ中間にある四日市市役所を過ぎると、ほとんど高い建物が見られなくなります。そうして辿り着いたJR四日市駅ですが、下の写真の通りとても閑散としています。

近鉄四日市駅の近くには商店街やショッピングセンターもあって多くの人で賑わっていたのですが、こちらはあまり人の気配がしません。駅のなかに入っても同じように人があまりいなくて、駅の建物も完全に昭和の雰囲気です。飲み物を買いたかったのですが、駅の中には売店もなく、周囲にコンビニもありません。そのかわりなのか自販機がずらっと並んでいて、その1つでお茶を購入しました。改札を入ると左手に古めかしい跨線橋があり、ここを通ってホームに向かいます。もちろんエスカレーターなんてありません。少し待ってやって来た電車は2両編成。あとから1日の乗降客数を調べてみたところ、近鉄四日市駅が約45000人、JR四日市駅が4600人と、なんと10倍近い差がありました。同じ駅名を名乗る駅で、これだけの格差があるところは珍しいのではないでしょうか。

実は1956年までは、近鉄線の四日市駅はJR四日市駅に隣接したところにありました。しかし、上の地図を見てもわかるように急なカーブを2つ通過しなければならず、それが輸送上のネックとなっていました。そこで、現在のようなルートに変更され、近鉄四日市駅ができたのです。ルート変更前、近鉄四日市駅の近くには諏訪駅という駅があり、周辺には商店街が形成されていました。このような経緯から、現在の四日市市の中心部も近鉄の駅の周辺になっているのです。ちなみに、諏訪駅周辺の店の1つだった岡田屋呉服店は、各地でショッピングモールなどを営む〝イオン〟の祖になった店です。 だったら、今度はJRの駅を移転すればいいのではないかとも思うのですが、それはできないことなのです。JR四日市駅のホームからは、ホームの両側に敷かれているいくつもの線路が見えます。そして、そこには貨物列車の姿が見えます。つまり、JR四日市駅は旅客駅としてだけでなく、海側の工場地帯への輸送を担う貨物駅としての役割もあるのです。先ほど末広橋梁を通過していった貨物列車もここから出発したのでしょうね。このようなことからJRの駅を移転することはできず、両駅の間には大きな格差が生じてしまっているというわけです。
公害や工業のイメージが強い四日市ですが、実際に訪ねてみるといろいろな顔があることがわかりました。それぞれの都市には多くの人々の生活があり、さまざまな役割があるわけで、1つだけのイメージで捉えてはいけないということが、改めてわかったような気がします。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。