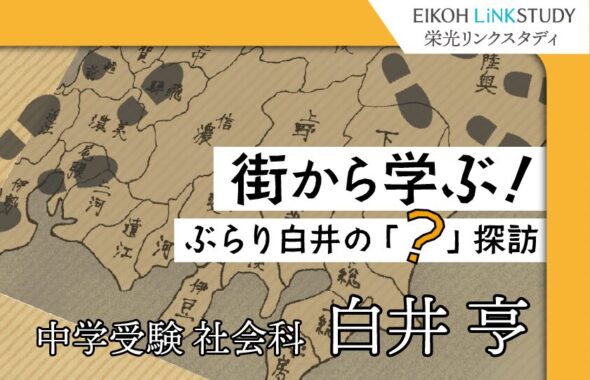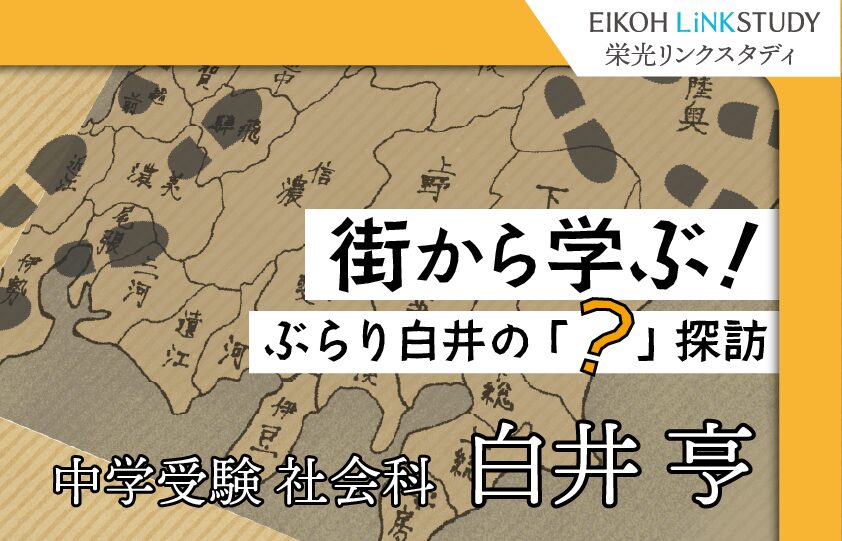
~愛知県名古屋市・豊明市
2つの有名古戦場跡編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
桶狭間の戦いといえば、織田信長の戦いのなかでもよく知られたものの1つです。教科書にも載っている有名な戦いで、リンストのテキストにも「尾張国(愛知県)の小大名であった織田信長は,1560年の桶狭間の戦い(愛知県)で,当時〝海道一の弓取り〟とよばれた今川義元を破り,天下にその名を知られるようになりました。」と紹介されています。
とてもよく知られた戦いなのですが、その古戦場跡とされる場所が2か所あることがわかりました。その1つは名古屋市に、もう1つは隣の豊明市にあります。隣接する自治体どうしで、お互いに「こちらが本家!」みたいな感じになっているのかと思ったのですが、実は桶狭間の戦いが起こった場所については諸説あって、確定はできていないようなのです。
また、昔の教科書では「信長は激しい雨の中を密かに進軍し、長い列をなして行軍する今川軍の側面を奇襲攻撃した」というようなことが書かれていたのですが、どうやらこれも実際とは異なるようです。
いろいろなことを聞いているうちにいくつかの「?」が頭に浮かび、やっぱり現地を訪れて自分の目で確かめてみたいと強く思うようになったのです。
まずは、下の地図を見ながら桶狭間の戦いの経緯を確認してみましょう。地図中にある「桶狭間古戦場公園」は名古屋市に、「桶狭間古戦場伝説地」は豊明市にあります。また、戦いが起こったときに今川軍の勢力下にあった場所は赤で、織田軍の勢力下にあった場所は緑で示しています。

1560年5月、大軍を率いて尾張国へ侵入した今川義元は沓掛城に入ります。城に入った義元は、松平元康に大高城へ兵糧を運び入れるように命じます。松平元康というのは後の徳川家康のことで、このころはまだ今川家に仕えていたのです。もし桶狭間で今川が勝っていれば、彼はずっと松平元康のままだったわけで、後に江戸幕府を開くこともなかったということですよね。桶狭間の戦いというのは、日本の歴史における重要な分岐点だったのかもしれません。
話をもとに戻しましょう。兵糧を運んだということは、義元が次に目指すはずだったのは大高城だったということが推測されます。織田方が築いた鷲津砦と丸根砦を攻め落としていることからも、その意図を読み取ることができるでしょう。鷲津、丸根の2つが今川方の勢力下に入ることで、沓掛城から大高城までの進路はほぼ確保されたと考えることができますね。おそらく義元もそのように考えたでしょう。この状況の中で、今川軍に比べて格段に兵の数が少ない織田軍が自分たちの近くまで来ているなどと想像することは困難だったかもしれません。諸説ありますが、織田と今川の兵力差はおそらく数倍はあったはずです。このような場合、一般的に兵力の劣る側は城に籠って敵を迎え撃ちます。
しかし、信長は籠城を選びませんでした。本拠地の清洲城を出た信長は、熱田神宮で軍勢を整えて戦勝祈願をしました。すでに鷲津砦と丸根砦は今川軍に攻略されており、先ほどの地図のような状態になっていました。信長は、善照寺砦まで進出し、今川軍の動きを注視します。そんなときに、義元は進軍を止めて桶狭間の地で休息をし、そこに織田軍が攻めかかるのです。
それでは、実際に2つの古戦場を訪ねてみることにします。

まず向かったのは、名古屋市にある桶狭間古戦場公園です。名古屋駅から名鉄電車に乗って20分ほどで有松駅に着きました。駅のすぐ南側には旧東海道が通っており、下の写真のような古い町並みがそのまま残されています。江戸時代の東海道には53の宿場が置かれていましたが、ここ有松は〝間の宿〟とよばれる、宿場と宿場の間の休憩所のような場所でした。旅人たちへのお土産品としてつくられた有松絞という絞り染めは人気が高かったらしく、有松にはこの染物で財をなした商人によって繁栄していたそうです。桶狭間に行く前に少しだけ、風情のある街の散策を楽しみました。

旧東海道を離れ、桶狭間古戦場公園に向かう道は上り坂になっていました。地図を見ても、このあたりは起伏の多い場所だということがわかると思います。ただ、標高差はそれほど大きくないので、上り坂といっても歩くのがきついほどの坂ではありません。しばらく歩くと左側に池があり、そのあたりからは下り坂になっています。こちらも緩い下り坂です。あとで調べてみたところ、この池は木曽川から知多半島に引いた愛知用水の一部になっているようです。有松宿から20分ほどで目的地の公園にたどり着きました。公園の中に入ってみると、そこには桶狭間で戦った2人の武将の像がありました。仲良く並べられている敵同士の2人の気持ちは複雑かもしれないですね(笑)

公園内には「今川義元戦死之地」と書かれた石碑や、義元が馬を繋いだとされる木、義元の首を洗ったとされる泉などがありました。また、合戦の様子を表したジオラマなどもあり、2010年にできた比較的新しい公園は、とてもよく整備された場所でした。さすがに大都市名古屋の公園だけあってお金をかけているなと思う一方、整備され過ぎているという感じも否めません。全体的な雰囲気は、古戦場跡というよりも住宅街の整備された公園という感じです。ただ、丘陵地にある比較的広い土地ではあるので、ここで両軍の戦いが起こったというのはあり得ることではないかと思いました。
近くに今川義元の本陣跡があるというので、公園を出て東のほうに向かいます。こちらも静かな住宅街で、家々の建ち並ぶ坂を上って行くと、その途中の住宅の前に立っていたのが下の写真の碑です。

やはり、こちらも古戦場の雰囲気はほとんど感じられません。そもそも、こんな坂の途中に本陣を置くでしょうか? 坂があるということは、当時のこの場所は山だったはずです。本陣を置くのなら、周囲を見渡せる山の上のほうに置いたほうが有利だと思うのですが、この場所は山の中腹です。古戦場公園はともかくとして、こちらの本陣については俄かには信じることができません。
今度は、豊明市にある桶狭間古戦場伝説地に向かいます。
本陣跡からまた坂を上り、再び住宅街を進んでいきます。歩いてきた道はほぼ平坦だったのですが、道の両側には坂道が見えましたので、やはりこのあたりも起伏の多い土地なのだということが実感できます。15分ほどで到着した目的地は、名古屋市のものほど広いスペースではありませんが、ちょっとした公園のような場所になっていました。ただ、周囲の雰囲気についてはこちらのほうが古戦場にふさわしい感じもします。下の写真を見てもわかる通り、石碑の立っている古戦場跡から道路を挟んだ向かい側には山があり、昔の教科書の記述のように信長が奇襲攻撃をかけるのであれば、この場所ということになるのかもしれませんね。

先ほどの公園と同じように、こちらにも今川義元戦死の地の碑や、義元の墓がありました。墓には花が供えられており、規模は小さいながらも地元の方々によって大切に守られているという感じがします。道路を渡ったところには高徳院という寺院があります。階段を上って門を通り抜けた先には、下の写真の「今川義元公本陣跡」と書いた石碑がありました。

全体的にはこちらのほうが古戦場らしい雰囲気があると思っていたのですが、この本陣跡は「?」をつけざるを得ませんでした。下の地図でもわかるように、本陣跡の奥には高徳院の境内があり、その背後には山があるのです。これまで多くの戦いを経験してきた義元が、こんな窪地のような地形のところに本陣を置くなどあり得ないと思うのです。それこそ昔の教科書に書いてあるように背後の山から急襲されたら大変なことになりますよね。
実際に2つの古戦場跡を訪ねてみたのですが、どちらも「こちらが本物だ」と判断するには決め手に欠ける気がします。昔の教科書の記述のイメージだと豊明市のほうなのですが、大軍が行動する場所としては少々狭すぎる感じがしました。また、名古屋市のほうは周囲が開けすぎているように思え、これだと信長の軍が近づいてくるのがわかるので、大将の義元が討たれてしまう前に策が打てたのではないかと感じたのです。そして、義元の本陣についてはどちらも山の中腹にあり、周囲を警戒しにくいのではないかと思いました。いくら兵力差があって油断していたとしても、ここは今川軍にとっては敵地なのです。経験豊富な戦国武将がそこまで油断するでしょうか?

桶狭間の戦いがこの周辺で起こったということは間違いないのでしょう。そうすると、次のように考えることはできないでしょうか。
まず、今川軍は沓掛城から大高城に向かっていたのですから、豊明市の古戦場跡付近を通ったというのは確実だと思います。しかし、このような狭いところで休息をとったわけではなく、この付近にあるどこかの山の上のほうに陣を敷いていたのだと思います。一方、織田軍は善照寺砦から出撃してきたのですから、やはり北の方角から近づいてきたのではないかと思います。周囲の地形を利用しながら、少しずつ今川軍に迫って行ったのでしょう。織田軍にとっては地元ですから、地の利を活かすことができるはずです。
しかし、それでも兵力差を考えると織田軍が有利とまではいかないでしょう。大将を討ち取るほどの大勝利ですから、他にも何か要因があるはずです。そこで、もう一度桶狭間の戦いについて調べてみたところ、2つのことに気がついたのです。
1つ目は、今川軍の兵力です。今川軍は確かに大軍ですが、丸根砦や鷲津砦の攻撃などに兵力を割いていました。その他にも別動隊があったかもしれません。そう考えると、桶狭間にいた今川軍の兵力というのは、そこまでの大軍ではなかったということになります。つまり、織田軍と今川軍の兵力は、通説で言われているほどの差ではないということではないでしょうか。
もう1つは織田軍の動きです。実は、信長本体が攻撃をする少し前に、中嶋砦にいた織田軍の一部が攻撃を仕掛けて撃退されているのです。このような状況から、今川軍は「しばらくの間敵が来ることはないだろう」と油断してしまったということはないでしょうか。
このような状況の中で、今川軍は豊明市のほうの古戦場近くで休息していました。そこに地形を利用しながら近づいていった信長率いる織田軍が攻撃をしかけたのです。通説で言われているように突然の豪雨もあったのだと思います。油断しているときに襲撃を受けた今川軍は混乱し、義元はそもそもの目的地だった大高城に向かおうとしたのではないでしょうか。その先には名古屋市のほうの古戦場があり、この付近で激しい攻防があったと考えることができます。こちらはある程度のスペースがありますので、大軍どうしの戦いがあったとしても不自然ではありません。その戦いの中で義元は討たれ、今川軍は敗走してしまうのです。つまり、豊明市の古戦場は桶狭間の戦いが起こったところ、名古屋市の古戦場は桶狭間の戦いの決着がついたところというわけです。
いろいろと書いてきましたが、これは歴史の専門家でもない私が実際に訪ねてみた印象から考えたものに過ぎません。いろいろと至らない点もあるかもしれませんが、散策も考察も〝楽しみながら〟しているのだということでご容赦願えればと思います。
毎年6月初めには「桶狭間古戦場まつり」というイベントが開催されます。このイベントは、名古屋市と豊明市の共同開催だそうです。武者行列も両方の古戦場に行くのだそうです。このことからも、両市にまたがるこの付近全体が桶狭間古戦場ということでいいのではないでしょうか。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。