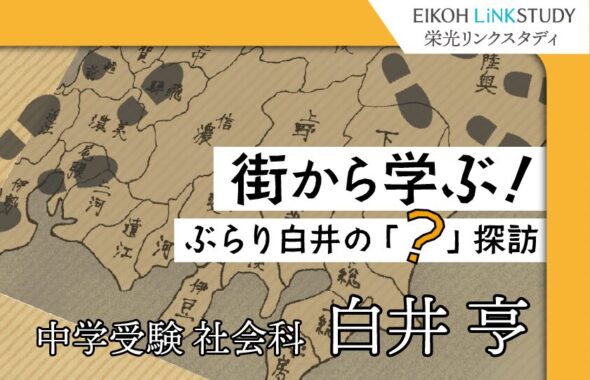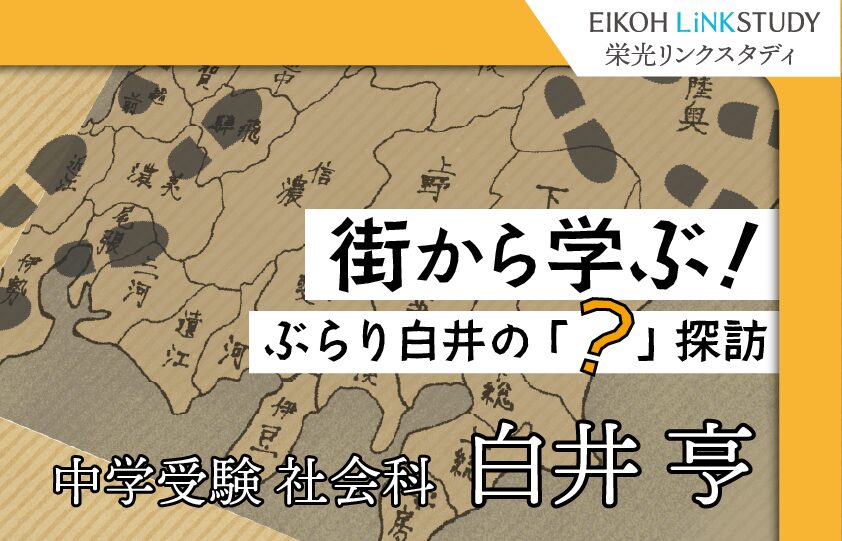
~山梨県大月市
なぜここに桃太郎??編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
桃から生まれた桃太郎が、犬、猿、雉を従えて鬼ヶ島の鬼を退治に行くという「桃太郎」の童話は、誰もが幼いころに聞いた話の1つでしょう。そして、その桃太郎のゆかりの地と言えば、岡山県と答える人が多いと思います。事実、岡山駅の前には桃太郎の像が置かれていますし、岡山土産の定番といえばきびだんごですからね。
ところが、東京からそれほど遠くないところに〝桃太郎推し〟の街があることを知っている人は、あまりいないのではないかと思います。…ということで、今回は桃太郎伝説の地(?)である、山梨県大月市を散策してきました。
大月市と聞いてもピンとこない人もいるかもしれないので、簡単に紹介しておきます。大月市は山梨県東部にある人口2万人ほどの市です。東京から富士急ハイランドや河口湖など富士山周辺の観光地に行ったことがある人は、ここを通っているはずです。中央本線の電車に乗って大月駅で乗り換えるのが富士急行線で、電車を利用したならばこの路線に乗って目的地に向かったはずです。また、自動車で中央自動車道を利用した場合は、大月ジャンクションが甲府方面と河口湖方面の分岐点になっています。下の地図を見ると、かなり山深いところにあるということがわかるでしょう。

大月駅まで乗った松本行きの特急列車は、後ろの3両が富士急行線に乗り入れる河口湖行きとなっており、車内で聞いたアナウンスによると、河口湖行きはかなり混雑していたようです。やはり大月は富士山観光への入口という位置づけで、ほとんどの人はここを通過していくのでしょう。私の乗った列車からも、大月駅で下車した人の数はそれほど多くありませんでした。
山小屋風の大月駅を出ると、さっそく下の写真のような桃太郎のモニュメントが目に入ってきました。少し見にくいかもしれませんが、下のほうには「ようこそ、桃太郎伝説の街、大月へ!」と書いてあり、大月が桃太郎推しであることをアピールしています。

駅の近くの国道沿いには「桃太郎神社」があるということなので、早速行ってみることにします。3分ほど歩いて着いたのですが、そこにあったのは下の写真のような、普通の店舗だったところに手作り感たっぷりの鳥居などの飾り付けをしただけのような施設…。朝早かったため中には入れなかったのですが、外から見るとたしかに小さな祠のようなものが置かれているのが見えました。左側にはハート型の絵馬のようなものが飾られていますが、どうやらこの神社は縁結びの御利益があるそうです。桃太郎と縁結びに何の関係があるんでしょうね?? 確かに家来の動物たちと出会ったのは縁なのかもしれませんけど…。ツッコミどころ満載の桃太郎神社ですが、もし開いていたとしても1人で入る気にはならなかったでしょうね。
国道を挟んだ反対側には「大月桃太郎伝説」と書かれた大きなピンクの看板を掲げたコンビニがありました。あくまでも個人の感想ですが、桃太郎神社よりもこちらのほうがインパクトがあるなと思いました。ちなみにこのコンビニは「モモタローソン」と呼ばれているそうです(笑)

ここまでのところ、街として桃太郎を強く推していることは理解できたのですが、その割にはちょっと残念な感じも否めません。そもそも、なぜ大月が桃太郎伝説の地とされるようになったのでしょうか?
大月まで乗ってきた特急電車は、大月駅の1つ手前で「猿橋駅」、もう1つ手前で「鳥沢駅」を通過しました。さらに甲州街道を東に進んだところには、「犬目宿」という宿場があります。猿橋も鳥沢も甲州街道の宿場町だったところです。つまり甲州街道沿いには、「犬目」「鳥沢」「猿橋」と、桃太郎に登場する動物の名がついた宿場が並んでいたのです。大月市の観光協会のホームページには、「大月 桃太郎伝説の里めぐり」というパンフレットが掲載されていて、それによると桃太郎は「犬目で犬と、鳥沢で雉と、猿橋で猿と出会って家来にした」のだそうです。
また、列車が大月駅に到着する直前には、右側の車窓に下の写真のような山を見ることができます。切り立った大きな岩の壁が特徴的なこの山は岩殿山といい、この山にある洞窟が鬼の住みかとなっていたのだそうです。見た目から険しい山なので鬼の住みかというイメージは納得できるような気もします。ただしこの山、歴史が好きな人ならすぐにピンとくると思いますが、この岩殿山には城が築かれていました。武田氏に仕えていた小山田氏の居城だった岩殿城は、「武田三堅城」の1つとして知られています。そのような城が築かれている山ですから、険しいのも当然と言えば当然なのです。

これだけの城でありながら、織田信長が甲斐に攻め込んだとき、岩殿城主だった小山田信茂は主君である武田勝頼が城に入るのを拒否しました。そして、行き場を失った勝頼は天目山(甲州市)で自害し、武田家は滅亡しました。織田軍に投降した信茂は「主君を裏切った」ということで処刑されてしまうのですが、実は信茂の行動はこの地の領民を守るためだったという説もあります。たしかに、勝頼が岩殿城に入っていればここで激しい戦いが起こったはずで、領民たちも多く犠牲になったことでしょうね。今となっては知る由もありませんが、もしそうならば鬼のイメージは薄らいでしまいそうですね。

さて、桃太郎が猿と出会った猿橋は、桃太郎の入った桃が流れてきたとされる桂川に架かる橋で、日本三奇橋の1つとしても知られています。せっかくなので、大月駅からバスに乗ってこの橋を見に行くことにしました。日本三奇橋とは、山口県岩国市の〝錦帯橋〟、長野県上松町の〝木曽の桟〟とこの猿橋の3つの橋のことで、どれも珍しい構造の橋となっています。アーチ形の橋が連なる錦帯橋はテレビなどでもよく見ることがあるので、知っている人も多いでしょう。木曽の桟は、残念ながら昔の姿を留めてはいないようです。
大月駅から15分ほどで猿橋のバス停に到着しました。下の写真を見ても、その珍しい構造がわかると思います。猿橋のかかるこの付近の桂川は、両側を切り立った崖に挟まれた狭い谷になっています。もし、大雨が降れば水量が増して、橋脚のある橋や水面に近い橋では流されてしまうでしょう。この場所に橋を架けるには、橋脚がなく、水面から離れたものにしなければなりません。
そこで用いられたのが「刎橋」という架橋方法です。まず、両岸の岩に穴をあけて「刎ね木」を斜めに差込みます。突き出た刎ね木の上に次の刎ね木を載せて、下の刎ね木よりも少し長く突き出させます。これを何度がくり返して橋を支える土台をつくり、その上に板を敷いて橋を架けていきます。下の写真を見ると、重ねられた刎ね木の上に橋が乗せられている構造がよくわかると思いますが、確かに珍しい橋ですよね。

猿橋は、ただ眺めるだけでなく渡ることもできます。橋の上から下を見ると、かなり高い位置に橋が架けられていることがよくわかります。ちなみに、猿橋という名は、猿がつながって深い谷を渡る姿を見てこの構造を思いついたということから付けられているそうです。どうも桃太郎の猿とはあまり関係がなさそうですね…。それはともかくとして、この橋自体は一見の価値があると思います。
猿橋の近くには、もう1つ興味深いものがありました。猿橋から階段と坂道を下って行くと、左側に下の写真のような崖が見られます。この崖は〝猿橋溶岩流〟と呼ばれており、10000年ほど前の富士山の噴火によって流れ出た溶岩がここまで流れてきたのだそうです。富士山からここまではおよそ30kmもありますが、溶岩は桂川に沿って流れ、ここまでたどり着きました。どれだけ多くの溶岩が流れ出たのか想像もつきませんが、この規模の噴火が起こったら大変なことになるということは容易にわかると思います。

さて、もともとのテーマは桃太郎でしたので、最後にそれに関わる場所に行ってみようと思います。30分ほど歩いたところに〝鬼の杖〟と書かれた場所を見つけたので、そこを目指してみることにしました。なんでも、岩殿山にいた鬼が、桃太郎に向けて投げつけた石杖が突き刺さったものなのだとか…。
ここに向かう途中で桂川に架かる橋を渡ったのですが、先ほどの猿橋と同じように橋の位置は川の流れている位置よりもかなり高いところにあります。桃太郎の話の冒頭では「おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川へ洗濯に…」とありますよね。道や家などがあるのは橋の高さのところですから、おばあさんはこの崖を降りて洗濯をしに行ったということですかね?? この点についても「?」と思わざるを得ないですよね。ちなみに、おじいさんの「柴刈り」というのは誤字ではないですからね。「芝刈り」だと思っている人がいるみたいですけど、そちらの方が誤字なのですよ。「柴刈り」というのは小さな雑木や枝を野山から採集することで、おじいさんは山に薪などを拾いに行ったのです。芝生の整備をしていたわけではありませんからね(笑)
さて、桂川を渡って坂道を登り、中央自動車道の下を通ってやって来た場所には、鬼の杖と書かれた看板と、透明なケースの中に入った鬼のジオラマが置かれていました。鬼が石杖を投げている様子を表しているようで、大月市の皆様には申し訳ないのですが、これがどうにも安っぽく見えてしまったんです。これなら何もないほうがいいんじゃないかと…。そして、その奥にあったのが下の写真の〝鬼の杖〟とよばれる石です。

正直なところ、これも「う~ん…」という感じですよね。石の大きさは高が125cm、幅が42cm、厚さが19cmあってそれなりに大きなものです。SNSには「鬼の杖と言われればそう見ていてくる」という記事もあったので、しばらくの間眺めていたのですが、私の目に鬼が投げた杖が見えてくることはありませんでした。…想像力が足りないんですかね??
ただ、このような形で地面に突き刺さっている石は珍しいので、どうやってこのようになったのかということについては、ちょっと興味があるかもしれません。この鬼の杖があるところの地名は「石動」というそうで、鬼が投げた杖が突き刺さったときに地面が揺れたことに由来するそうです。そのことから考えると、この石も地震などによってこのようになったのではないかと想像できるのですがいかがでしょうか?
その他にも、鬼が酒盛りに使ったとされる〝鬼の盃〟という手水鉢や、鬼の血が浸み込んで赤くなったという土が見られる〝鬼の血〟といった場所もあるようなのですが、さすがにそこまで行ってみる気にはなれず、そのまま猿橋駅へと向かい、次の目的地を目指すことにしました。
町おこしの一環として、大月市が桃太郎を強くアピールしようとしていることはわかりました。そもそもこの地に桃太郎は無理があるのでは?? …というのはさておき、観光名所にしたいのなら、もう少しがんばっていただきたいなというのが正直な感想でした。富士山方面に向かうインバウンドが立ち寄ってくれるような、魅力的な街になって欲しいものです。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。