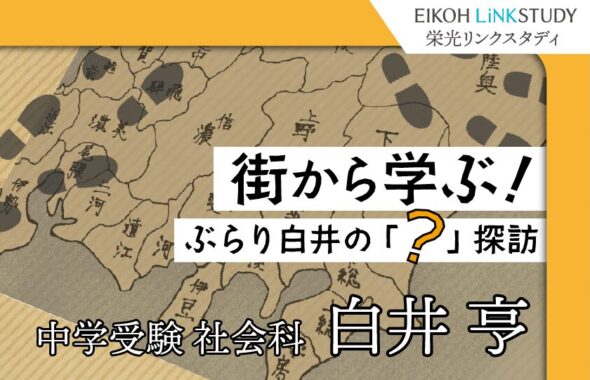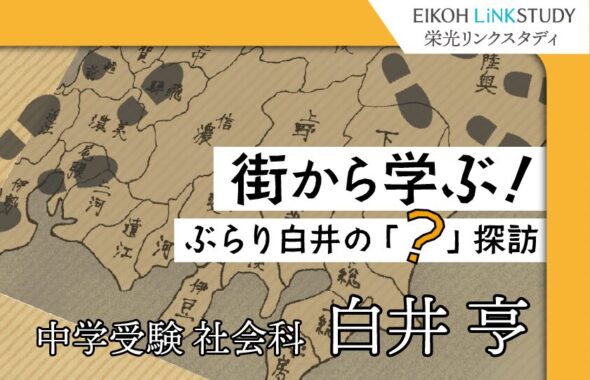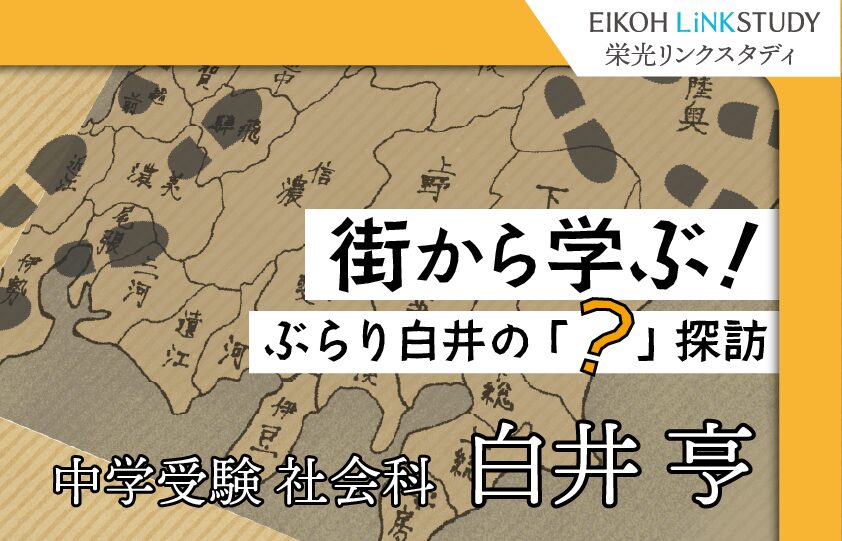
~福井県敦賀市
港と歴史と鉄道の町編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
2024年3月に北陸新幹線が延伸され、東京駅でも〝敦賀〟の文字を見かけるようになりましたが、それまでは東京に住む人たちにとって、それほど馴染みのある地名ではなかったように思います。そもそも敦賀って正しく読めなかった人も多かったのではないですかね。
ちょっと気になったので、敦賀の地名由来を調べてみました。いくつかの説があるようですが、敦賀市のホームページには以下のように書かれていました。遥か昔、朝鮮半島から都怒我阿羅斯等という人物がこの地にやって来たそうです。その人物の額に角があったことから角額という地名となり、さらにこれが縮まって角鹿となって敦賀になったのだそうです。都怒我阿羅斯等ってたぶん「つのがあるひと」ですよね(笑)
現実に角がある人がいるわけはないので、おそらく兜のようなものを被っていて、それが角に見えたのでしょうね。敦賀駅前には都怒我阿羅斯等の像が置かれていますが、この像も角のようなデザインのある兜をつけています。

下の地図で敦賀市の位置を確認してみましょう。
北には敦賀湾があります。三方を陸地に囲まれた深い入江となっているこの湾は天然の良港となっていることがわかると思います。古代には中国東北部にあった渤海という国からの使節が来航し、江戸時代には東北地方や北陸地方の米を積んだ北前船の寄港地として栄えていました。現在の敦賀港からも、新潟港と秋田港を経由して苫小牧港に向かうフェリーが発着しています。

地形の恩恵を受けて栄えてきた敦賀ですが、近代になって交通の主役が鉄道になると、その地形が大きな障害となってしまいます。明治時代になると、日本各地に鉄道を建設する計画が立てられ、その最初の4つの路線のうちの1つが敦賀と京都を結ぶものでした。しかし、地図を見てわかる通り、敦賀は三方を山に囲まれた土地なので、どの方面に進むにも山を越える必要がありました。鉄のレールと鉄の車輪で動く鉄道は勾配に弱く、ここに鉄道を建設することはとても困難なことだったのです。難工事の末に開通してからも、さらに困難は続きます。琵琶湖の北部から敦賀へのルートは、急な坂とトンネルが連続するものでした。当時は蒸気機関車を使用していたため、坂を上り切れずに一度坂の下まで引き返してから再度やり直すといったこともあったそうです。トンネル内では煤煙が充満し、機関士が窒息死するという事故も発生しました。さまざまな困難を乗り越えてでも鉄道の建設を急いだということは、それほど敦賀の存在が重要だったということでしょう。
私の乗った新幹線も、敦賀駅到着前にとても長いトンネルを通りました。調べてみたところ、この新北陸トンネルは長さが19,760mもあり、北陸新幹線では2番目に長いトンネルだそうです。 そうそう、東京から敦賀に来るには北陸新幹線を使ったルートが最速ルートではないんです。北陸新幹線に乗ると3時間余りですが、東海道新幹線で米原に出てそこから北陸本線の特急に乗り継ぐと2時間50分ほどで着き、料金もこちらの方が安く済みます。乗り換えなしで行かれる北陸新幹線か、乗り換えの手間はあるけど安くて速い東海道新幹線か、みなさんが敦賀に行くならどちらを選びますか?

到着した敦賀駅は、上の写真でもわかるようにとても大きな駅です。写真ではわかりにくいと思いますが、横長の窓がある位置に新幹線が止まっています。かなり高い位置ですよね。実際に、新幹線を降りてから駅を出るまではなかなか大変でした。まず、新幹線ホームから長いエスカレーターで乗り換え改札があるフロアに行きます。改札を出て前方に進んでいくと、右の方にまたエスカレーターがあります。これを下ると、もともとあった敦賀駅の在来線ホームを跨ぐ長い跨線橋があり、突き当たるとまた右に下りるエスカレーターがあります。これを下るとようやく左側に出口があるのです。新幹線の駅というのは大きなものが多いですが、出口までこれだけ時間がかかる駅も少ないのではないかと思います。

敦賀駅からバスに乗って最初に目指したのは金ヶ崎城です。歴史好きならばこの城の名は聞いたことがあると思いますが、海に突き出した山の上にあるこの城は、源平合戦や南北朝時代の足利氏と新田氏の戦いなど、数々の戦いの舞台となってきたところです。そのなかでも特によく知られているのが、1570年に起こった〝金ヶ崎の退き口〟とよばれる戦いでしょう。この戦いでは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人が同時に危機に直面したとされています。
越前の朝倉氏を攻めるために出陣した信長は、金ヶ崎城を攻撃して落城させます。そのまま越前国内に攻め入ろうとした信長に、浅井長政が裏切ったという知らせが届きます。このままでは織田軍は挟み撃ちにされることになり、信長自身も危険にさらされます。やむを得ず撤退を決めた信長は山中を駆け抜け、3日後に京都に辿り着きました。そのとき信長の供をしていたのは、わずか数十騎の兵のみだったといいます。そして、この撤退戦において〝殿〟を務めたのが秀吉だったとされています。〝殿〟とは、軍が撤退するときにいちばん最後になる部隊のことで、攻めてくる敵を防ぎながら退却をしなければならないため被害も多くなるという、とても困難な任務です。また、家康は信長から撤退のことを知らされずにいたため退却が遅れて、結果的に秀吉とともに殿を務めることになったと言われています。そして、2人の見事な活躍によって、織田軍は無事に撤退することができたというのです。でも、私はこの話にちょっと疑いを持っています。
まず秀吉ですが、このころの秀吉はまだ木下藤吉郎という名で、織田家の中では比較的軽い身分の武士です。そんな人物に大事な任務を任せるでしょうか? また、家康は信長の部下ではなくあくまでも同盟者です。戦いに協力している同盟軍に大事な連絡をしないなどということはあるのでしょうか? あくまでも個人の考えですが、天下を取った秀吉が信長に仕えていたときのことを脚色してこの話を広め、次に天下を取った家康が秀吉をしのぐ活躍をしていたと思わせるために脚色したというのが真相なのではないかと思うのですがいかがでしょう?
ここでは城跡のある山の麓に建てられている金崎宮をお参りするだけの予定でした。金崎宮は、金ヶ崎の退き口の経緯から「難関突破」にご利益があると言われています。階段を上ってお参りをした後、港の景色を見下ろそうと本殿の左に進んでいきました。すると、その先に金ヶ崎城への登り口があり、それを見つけた私はどうしても城跡まで行ってみたくなってしまったのです。
地図で見る限りたいした距離ではないと思っていたのですが、坂を上り、階段を上り、また坂を上り…となかなかゴールが見えてきません。まだ3月だというのに汗を流しながら辿り着いた城跡からは、下の写真のように敦賀湾を一望することができ、天然の良港を実感することができました。
しばらくの間この景色を楽しんだ後、帰りは上って来るときとは別のルートを選んで見ました。こちらのほうがこの城での戦いの様子が感じられる場所がいくつかあって興味深かったのですが、上るのはこちらのほうがさらにきついルートになるかもしれません。

金ヶ崎城をあとにして港のほうに向かって少し歩いたところに、下の写真のような線路がありました。錆びついたレールからもわかると思いますが、この線路はすでに使われていないものです。港のほうに延びているこの線路はいったい何のためにつくられたのでしょうか?

この線路は敦賀駅から分岐して敦賀港へ向かう路線の跡で、かつてはとても重要な路線だったのです。
1902年に、ウラジオストクからロシア国内を横断してヨーロッパに向かうシベリア鉄道が開通すると、敦賀~ウラジオストク間の定期航路が就航します。そして、1912年には東京からここ敦賀港への直通列車が走るようになります。かつては東京からの列車がこの線路を通っていたということですね。この列車は「欧亜国際連絡列車」と呼ばれており、このルートを使うと東京からパリまで17日間で行くことができたそうです。船を利用すると1か月程度かかっていたので、これが当時の最速ルートだったのです。敦賀港駅の駅舎を利用した敦賀鉄道資料館には、東京発ベルリン行きの切符が展示されています。この付近には、下の写真の赤レンガ倉庫などもあり、敦賀の観光スポットの1つとなっています。赤レンガ倉庫の右の方には、福井県内で何度も見かけた恐竜博士の姿も見えますね。

敦賀港から多くの人々がヨーロッパへ旅立っていた一方、日本に来るために敦賀港にやって来た外国人もいました。
1940年、ナチスドイツによる迫害から逃げてきたユダヤ人たちが、リトアニアにあった日本領事館にビザの発行を求めて集まってきました。ビザとはその国への入国許可証のようなもので、ユダヤ人たちは日本を経由して、ナチスの手の届かないところへ行こうとしたのです。このときに領事を務めていたのが杉原千畝という人物です。当時のドイツは日本と同盟を結んでいましたから、日本政府はユダヤ人たちへのビザの発行を許可しませんでした。しかし、このままではいずれ殺されてしまう人々を目の前にした杉原は政府の命令に背き、独断でビザを発行しました。やがて、杉原に対して日本政府からの帰国命令が出されます。杉原は帰国の途に就く列車が動き出すまで、ビザの発行を続けたそうです。この杉原の行動によって命を救われたユダヤ人は6000人にもなるそうです。リトアニアからロシア国内を経由し、ウラジオストクから船に乗り込んだユダヤ人たちが上陸したのが、この敦賀港なのだそうです。敦賀港には敦賀ムゼウムという資料館があり、これらのことについて学ぶことができるようになっています。第二次世界大戦中に大変な苦難にあったユダヤ人ですが、そのユダヤ人のつくった国であるイスラエルの現状を考えてみると、なんだかとても複雑な気持ちになります。
さて、敦賀港の周辺を散策した後は、氣比神宮に向かいます。せっかくなので、先ほどの廃線跡まで戻って、線路沿いに歩いてみることにしました。しばらく進んでいくと線路が途切れ、その行く手に国道8号線が見えてきます。そして、国道の下をくぐるトンネルがあるのですが、古くからあるものには見えないのです。少なくとも、この路線ができたときのものでないことは確かでしょう。調べてみたところ、このトンネルができたのは、この路線を通る列車がなくなった後のようです。もしかしたら、いずれこの線路を再利用するつもりでもあるんでしょうか? 新幹線も開通したことだし、敦賀駅と港の観光施設を結ぶトロッコ列車なんかが走ったら楽しそうですね。
線路を眺めながらゆっくりと歩いたので、20分ほどで氣比神宮の東門にやって来ました。境内に入ると、左側に2つの社があり、そのうちの1つが角鹿神社です。最初に書いた通り、角鹿は敦賀の地名の由来になったものです。そして、その由来になっている都怒我阿羅斯等が祀られているのがこの角鹿神社です。 氣比神宮というと下の写真の鳥居が有名です。この鳥居は、広島の厳島神社、奈良の春日大社の鳥居とともに日本三大鳥居の1つに数えられているもので、高さが11mもある大鳥居はとても立派なものでした。敦賀駅から続く道にも面しており、普通に考えれば大鳥居のあるほうが氣比神宮の表参道ということになるのでしょう。

私が入ってきた東門は、本殿のあるところを挟んでその反対側になるわけですから、どちらかというと裏の入口のような場所だと思います。そのような場所に、敦賀の由来となっている名の神社があるというのに不自然さを感じますよね。角鹿神社の鳥居の横に説明版が建てられていたので、その記述を読んでみたところ「往古は東門口が表参道だった」と書かれていました。往古というのは「昔」という意味です。つまり、昔は多くの人がこちらの入口から入って参拝をしていたということです。しかし、現在の東門の入口には鳥居もなく、昔のこととは言ってもこちらが表参道だったとは俄かには信じがたい佇まいです。なぜ昔は東門が表参道とされていたのでしょうか?
ここでふと思い出したのは、私が氣比神宮にやって来たのは敦賀港の方面からだということです。敦賀はもともと港町として栄えていたところです。鉄道や道路などの陸上交通が発達するまでは、敦賀を訪れる人の多くが海からやって来たのではないでしょうか。昔の航海は今とは比べられないくらい危険と隣り合わせのものでした。海からやって来た人々は、無事にたどり着けたことを氣比神宮に感謝したのでしょう。これから海に向かう人々も、氣比神宮に航海の安全を祈ったのでしょう。そのため、かつての氣比神宮の表参道は港の方面にあたる東門だったです。氣比神宮の主祭神となっているのは伊奢沙別命で、氣比神宮のホームページには「食物を司り、また古くより海上交通、農漁業始め衣食住の生活全般を護り給う神」と書いてありました。敦賀の港にやって来た人々は、食べ物などのさまざまな物資をこの地にもたらしたことでしょう。かつての敦賀はとても豊かな土地だったということです。その豊かさをもたらした海の方向に表参道があったというのは、かつての敦賀の繁栄の理由を考えれば当然のことなのです。しかし、近代になって鉄道が開通し、敦賀に物資をもたらすのは海から陸に変わります。そのため、氣比神宮の表参道も敦賀駅からの参拝に便利な現在の位置になったんですね。
この後は、日本三大松原の1つとなっている気比の松原や、幕末の水戸藩で尊王攘夷を唱えた天狗党の墓などを訪れようと思っていたのですが、帰りの電車を考える少々厳しい時間になってしまいました。原因はまちがいなく金ヶ崎城に登ったことですね。お昼もだいぶ過ぎていましたのでおなかもすいてきた私は、それらの訪問はあきらめ、そのまま駅まで歩いて戻ることにしたのです。
氣比神宮から敦賀駅への道沿いには、「宇宙戦艦ヤマト」や「銀河鉄道999」の場面を再現したモニュメントが並んでいます。全部で28体あるこれらのモニュメントは、敦賀港開港100周年の1999年に「日本でも有数の鉄道と港の町」である敦賀のイメージに重ね合わせて設置されたのだそうです。どちらのアニメも子どものころに見ていたものだったので、1つ1つ懐かしい気持ちで眺めていったのです。敦賀駅から氣比神宮へ向かって右側の歩道には「銀河鉄道999」、左側の歩道には「宇宙戦艦ヤマト」のものがありますので、どちらも見たいという場合には、行きと帰りで別の歩道を歩いていくといいと思います。敦賀駅からバスを利用してしまった私は、何度か横断歩道を渡りながら両側にあるいくつかのモニュメントを確認していきました。そして、駅近くのお店で福井名物の〝越前おろし蕎麦〟をいただいてから帰路に就いたのです。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。