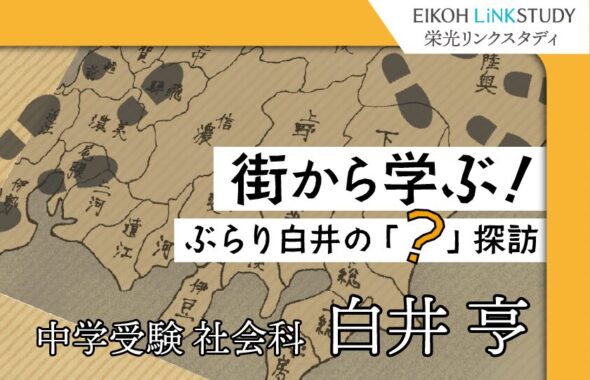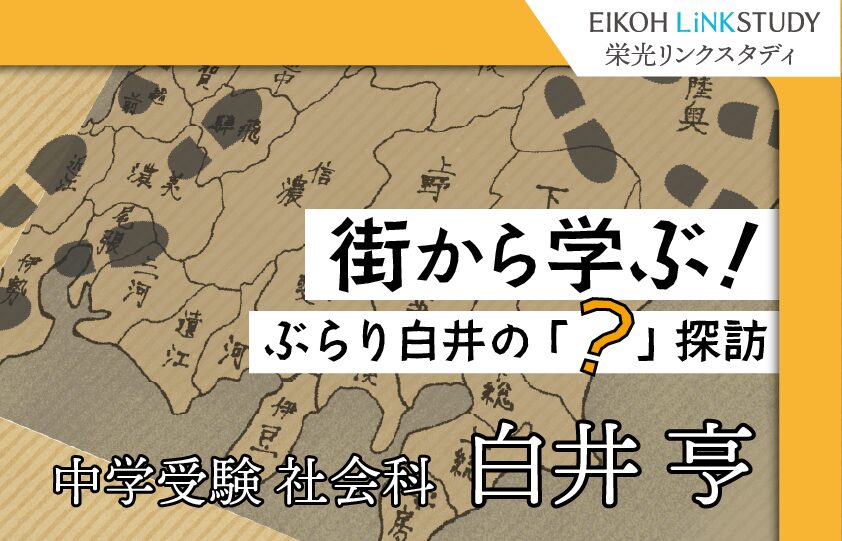
~福井県福井市
甦った戦国の城下町編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
現在の日本には47の都道府県がありますが、昔の日本は68の国に分けられていました。68の国は「大国・上国・中国・下国」の4つのランクに分けられていて、北陸地方で唯一「大国」となっていたのが越前国、現在の福井県北東部にあたる地域です。
北陸地方には、新潟県、富山県、石川県、福井県の4県がありますが、福井県民に失礼なのは承知の上で申しますと、おそらく福井県をトップに持っていく人はほとんどいないのではないかと思うのです。1つの例として人口に注目してみても、福井県の人口はおよそ74万人で、北陸地方の中ではもちろんのこと、全国でも5番目に人口が少ない都道府県ですからね。
今回は、国のランク付けがなされた古代ではなく、戦国時代の越前国のことを取り上げます。
戦国時代の越前国は朝倉氏によって治められ、およそ100年もの長い間、平和と繁栄が保たれていました。多くの人が朝倉氏に対して抱いている印象は、信長によって滅ぼされた大名というものではないでしょうか。しかし、戦国時代にそれだけの長い間1つの国を保つことができたというのは、優れた治政がおこなわれていたということにもなるでしょう。その朝倉氏の栄華を今に伝えるのが、福井市街地の南東10㎞ほどのところにある一乗谷遺跡です。
下の地図で一乗谷の位置を確認してください。福井市街から足羽川に沿って上流に向かい、平野から山間部に入り、さらにその支流が刻んだ谷に沿ったところにあるということがわかりますね。戦国時代のことですから、敵からの防御ということを最優先に考えてこの地を選んだのでしょうね。

一乗谷遺跡は、信長によって焼かれた後、その大半が地中に埋もれていました。1967年から始まった発掘調査によって当時の遺構が数多く見つかり、現在では当時の城下町全体が遺跡として保存されています。これだけの規模の遺跡ですので、以前から訪れてみたいと思っていたのですが、今回その願いがようやく実現したのです。
さて、福井駅から出るJR越美北線には一乗谷駅という駅があるのでこれを利用すればよさそうです。そう思って調べてみたところ、この路線、なんと1日に8本しかないという超ローカル線でした。また、福井駅から出るバスもあるのですが、こちらも1日に7本だけ。さらに、遺跡内を移動するのに循環バスが運行されているらしいのですが、運行されるのは休日のみ。あいにく訪れる日は平日であるため、これも利用できません。公共交通機関を使うと、なかなか訪れるのが困難だということがわかりました。しかし、これだけの遺跡ですから、あまり時間の制約を受けるのも不本意です。…ということで、今回は福井駅からレンタカーを利用することにしました。これで、心ゆくまで戦国時代を楽しむことができそうです。
福井駅からおよそ20分で一乗谷の入り口にある「朝倉氏遺跡博物館」に着きました。まずはここで一乗谷遺跡の予習をしようと思います。

博物館には、発掘調査で見つかった数多くの出土品や、当時の一乗谷の町並みを復元したジオラマ、さらに朝倉氏当主の館の復元などがあり、それぞれがかなり見応えのあるものでした。その中でも特に印象に残ったのは、博物館建設にあたっての発掘調査で見つかった遺構が、そのまま展示されているスペースです。石積みの遺構は、川に築かれた港のものと推測されているのだそうです。
前述した通り、一乗谷は敵からの防御には適した地形ですが、それだけで城下町の繁栄を保つことはできません。戦国大名がその勢力を保つためには〝富国強兵〟の政策が必要なのです。一乗谷の位置を見て「?」と思っていたことは、この〝富国〟の部分はどうしていたのだろうということでした。
一乗谷は、一乗谷川によってできた谷に沿って築かれた城下町です。一乗谷川は谷の出口で足羽川に合流し、その足羽川は九頭竜川に合流して日本海へと注ぎます。つまり、一乗谷は川の運搬ルートを使えば、日本各地だけでなく、海外との交流も可能だったのです。実際に、一乗谷遺跡では中国製の陶磁器やベネチアンガラスも見つかっているそうです。今まさに目の前に見ているこの場所にたくさんの船がやって来て、さまざまな物資が一乗谷の城下町に運ばれてきたのでしょう。当時の港の賑わいを思い描きながら、しばらくの間石積みを眺めていました。
さて、いよいよ一乗谷へ入っていきます。
最初に訪れたのは、下の写真の〝下城戸跡〟です。ここは城下町の入り口にあたるところで、きっと当時は堅固な門が築かれ、警護の武士たちがここを守っていたのでしょう。ここから上流2㎞ほどのところにある〝上城戸跡〟までが、一乗谷の城下町ということになります。目の前にある大きな石と土塁はとても立派なもので、ここを破って攻め入るのはなかなか難しいのではないかと思います。

下城戸跡からしばらく進んだところにある駐車場に車を置き、遺跡の中心部の散策をしていきましょう。
まず向かったのは、朝倉氏5代義景が住んでいたという〝朝倉館跡〟です。下の写真は、その入り口にある〝唐門〟で、写真からもわかるように、武家の館らしく堀と土塁に囲まれています。門をくぐって中に入ると広いスペースがあり、当時は17棟の建物があったのだそうです。

今は礎石が残るのみですが、それだけでもなかなかの規模の館だったことがわかります。礎石を間近に見ることができるガラス張りの床が設けられているのですが、メンテナンス中で使用できなかったのは残念でした。それでもこの遺跡の様子から当時の華やかな様子を想像することは難しいことではないでしょう。
館の背後は山になっており、そこに上って行くことにします。館の様子を上から眺めると、その規模の大きさがはっきりとわかります。礎石の数の多さからは、当時の繁栄の様子を感じることができます。
一乗谷遺跡には、4つの庭園跡が見られます。
1467年に起こった応仁の乱によって京都は灰燼に帰してしまい、当時の文化人だった多くの貴族や僧たちが都を離れていきました。一乗谷は京都からそれほど遠くありませんから、朝倉氏を頼ってきた人も多くいたことでしょう。都の文化の影響を強く反映したこれらの庭園は、当時の最先端の文化だったのかもしれないですね。下の写真を見てください。整然と配置された大きな石からも、美しい庭園の様子がよくわかると思います。写真の真ん中あたりに大きな石がありますが、その左側には階段状の石組みがあるのがわかると思います。おそらくこれは滝ですよね。大きな石の間を滝が流れ、その水が池に注いでいる様子を想像してみてください。何とも優雅な風景ですね。このような遺構が見られることはとても貴重なもので、1つ1つの庭園の様子を想像しながら、当時の大名や貴族の気分に浸るのも楽しいものです。現在見ることができるのは4つの庭園跡だけですが、一乗谷遺跡全体では15ほどの庭園があったということが確認されているそうです。

一乗谷は1つの町であると同時に、戦国大名の拠点でもあります。当然ですが、戦いのための施設も築かれていたわけで、山を登っていくと、下の写真のような土塁の跡や、深い堀の跡を目にすることができます。一条川沿いの谷の上流と下流には城戸が設けられ、その両側にある山にはこのような土塁や堀が築かれていることから、やはり一乗谷は戦国時代の遺跡なのだということを改めて感じさせられるのです。優雅な庭園跡と、武骨な土塁跡が近いところで見られるのも、一乗谷遺跡の興味深いところでしょう。

さて、一乗谷遺跡の目玉となっているのが、復元された当時の町並みです。
発掘された建物の礎石や出された品に基づき、当時の城下町が忠実に再現されています。下の写真を見てください。まるで、戦国時代にタイムスリップをしたようで、当時の人々が建物から出てきてもまったく違和感を覚えることはないでしょう。昔のものを再現した施設の中には、正直がっかりしてしまうものも少なくないのですが、この復元町並はとても素敵でした。

ところで、一乗谷遺跡には日本で初めて発見されたものがあるのだそうですが、何だかわかりますか?
答えは〝トイレ〟です。一乗谷の城下町では、庶民の家一軒一軒に、トイレと井戸の設備があったそうです。先ほどの庭園などはあくまでも特別な身分の人たちのものですが、一般庶民も文化的な生活をしていたということが伺えることに、この城下町のレベルの高さを感じます。きっと朝倉氏は良い政治をしていたのでしょうね。しかし、この繁栄は織田信長の侵攻によってすべて消え去ってしまいます。歴史のテキストには、信長・秀吉・家康の三英雄が戦国時代を終わらせて平和をもたらしたというようなことが書いてありますが、一乗谷に住んでいた人々にとって、それは本当に幸せなことだったのでしょうか? それは本当の平和なのでしょうか? なんだか複雑な気持ちになってしまいました。
室町幕府最後の将軍となった足利義昭は、この一乗谷に9か月ほど滞在しています。兄である13代将軍義輝が暗殺された後、この地に逃げてきた義昭は、当時の朝倉氏当主だった義景に上洛(都に上ること)を要請します。しかし、義景は義昭の願いに応じることはなく、やがて義昭は朝倉氏のもとを去って信長を頼るのです。
一般的には、このような義景の姿勢は消極的であるというように評価されることが多いようです。しかし、この一乗谷の様子を見て私は思ったのです。義景にとって上洛というのは危険な賭けであり、一乗谷の繁栄を守るためにもそのような危険な選択をすることはできなかったのでしょう。結果的に朝倉氏が滅亡してしまったため、義景は低い評価を受けていますが、当然の判断をしたに過ぎないのではないかと思うのです。

一乗谷で足利義昭が住んだのは、上城戸跡よりさらに上流にある場所でした。本来ならば、城下町の内側に住まいを設けるべきなのでしょうが、およそ10000人もの人々暮らしていたこの狭い谷には、そのスペースは残されていませんでした。身分の高い人の屋敷ですからある程度の広い敷地は必要です。その敷地を確保することができなかったため、義昭の御所は上城戸の外に置かれたわけです。もしかすると、このことも義昭にとっては不満だったかもしれないですね。身分の高い人はわがままですから(笑)
上の写真でもわかるように、現在のこの場所には何もありません。しかし、ここには足利義昭が暮らしていて、その義昭に仕えていた明智光秀もここにいたのです。そして、その光秀の尽力によって義昭は信長と出会い、信長の力によって室町幕府15代将軍となるのです。ここは、まちがいなく戦国時代の歴史が大きく動いた場所なのだと思うと、とても感慨深いものがありました。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。