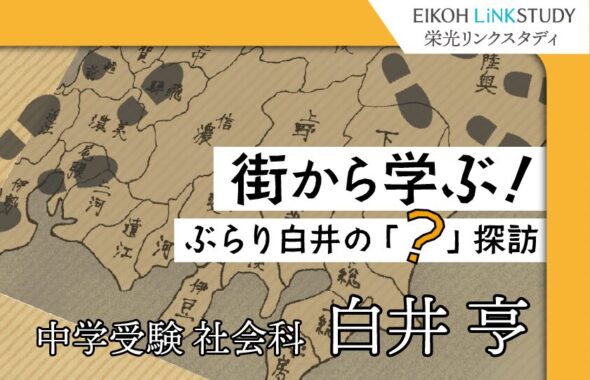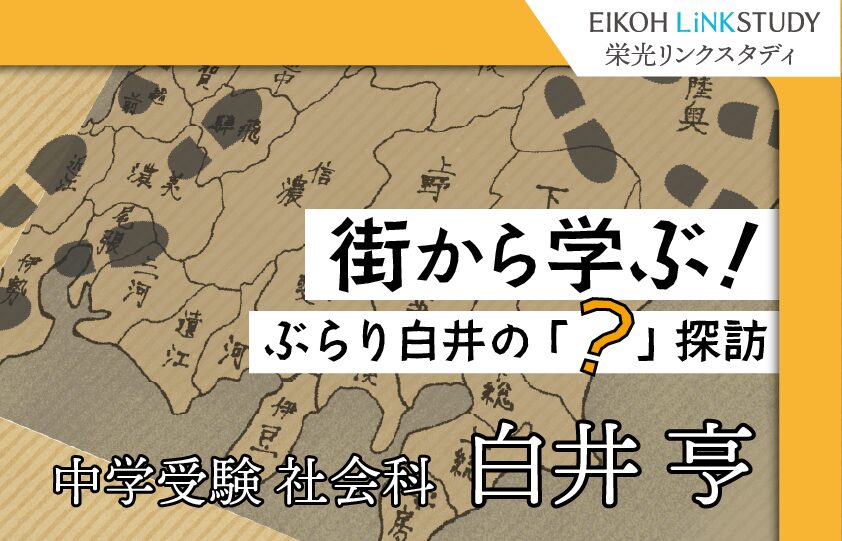
~東京都渋谷区
大都会の奇跡の森編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
下の写真は、東京都心を空から見たものです。大都会東京は、ご覧の通りほとんどがグレーの世界ですね。そんな無機質な色のなかに4か所、大きな緑がその存在を主張していることがわかります。東から天皇陛下御夫妻のお住まいや宮内庁がある皇居、皇室の方々のお住まいがある赤坂御所、戦前は皇室庭園だった新宿御苑となっており、いずれも皇室に関わる場所です。そして、4つのなかでも最も濃い緑になっているところが、今回のテーマとなっている明治神宮です。

その日は新宿で用事があったのですが、思いのほか早く済んでしまいました。帰宅するのも少し早いなぁと思っていたところ、ふと思い立って明治神宮まで行ってみることにしたのです。新宿から原宿まで山手線で2駅分ですから、歩くにはちょうど良さそうです。
西口の超高層ビル街を南下し、甲州街道を横断するとその先は渋谷区になります。…ということは、もしかして新宿駅も半分は渋谷区? と思って調べてみたら、やはり新南口やバスタ新宿は渋谷区になっていました。
ここからは大通りを避けて路地に入っていきます。新宿や渋谷と聞くとあの喧騒を思い浮かべてしまいますが、このあたりは静かな住宅街が続いています。小田急線の南新宿駅脇の踏切では長いこと待たされましたが、のんびり気分で歩いているせいかイライラすることもありません。踏切の先は少し下り坂になり、また上っているので、昔は川でもあったのかもしれないですね。
…と、いろいろなことを考えながら歩いていたら、程なく北参道の鳥居に到着しました。ここまでかかった時間はだいたい30分くらい、ほぼ予想通りですね。ここで一礼して境内に入ると、両側には森が広がります。この日は天気の良い日だったのですが、歩き進んでいくにつれ日差しが遮られ、薄暗く感じるようになっていきます。
ここ明治神宮の北には新宿、東には原宿、南には渋谷と、東京でも特に人の多い町に囲まれているということに気がつきました。大都会のなかによくこれだけの森が残ったものだと思ってしまいそうですが、この森は「残った」ものではなく、人工的につくられたものなのです。

明治神宮ができたのは、今から100年ほど前の1920年のことです。「今昔マップ」で見てみたところ、明治時代の終わりごろのこの地は〝南豊島御料地〟となっており、そのほとんどが荒れ地です。明治時代初期、あの西郷隆盛は、現在の目黒区駒場のあたりでうさぎ狩りを楽しんでいたそうです。駒場は明治神宮の南西2㎞あまりのところにあります。かつてのこの界隈には、広大な自然が広がっていたのでしょうね。下の地図でもわかる通り、明治神宮と隣接する代々木公園があるところは、2つの谷に挟まれた台地になっています。台地は水の便が悪いですから、荒れ地だったのも納得できますね。

ところが、地図をよく見てみると〝明治神宮御苑〟のあたりに、現在と重なる部分を見つけることができたのです。南池のあたりには池らしき形が読み取れますし、菖蒲田のあたりには湿地らしい記号が書かれています。どうやらこの部分だけはただの荒れ地ではなさそうですね。

御苑も気になりますが、まずは本殿に向かって参拝を済ませることにします。この日は平日だったのですが、下の写真のように多くの参拝客で賑わっていました。インバウンドの姿も数多く見ることができ、外国人にとっても日本の人気観光地の1つになっているのでしょうね。
明治神宮は、初詣に参拝者数が全国で最も多いところとしても知られ、その数は300万人にもなるそうです。大阪市の人口が280万人弱ですから、それよりも多い数の人がここを訪れているというわけですね。私は人がたくさん集まる場所が嫌いなので、おそらくお正月の明治神宮には一生来ることがないと思います(笑)

参拝を済ませた後は、明治神宮御苑に向かいます。ここは500円の拝観料がかかるのですが、せっかくなので入って見ようと思います。この500円は〝御苑維持協力金〟とされていて、そういう名称だと「それならしかたないよね」と納得して払うことができるような気がします。
江戸時代、この場所には井伊家の下屋敷がありました。下屋敷というのは大名の別邸として役割を持つ屋敷で、その多くは江戸の郊外につくられ、庭園などを備えたものになっています。大名にとっての憩いの場であり、大事な客を接待するようなところでもありました。
井伊家といえば、幕末の大老井伊直弼を思い浮かべる人も多いでしょう。末期の江戸幕府を支え、多忙だった直弼も、もしかしたらこの場所に来て癒されたりしていたかもしれませんね。そういえば、井伊直弼は、明治新政府の中心となった薩摩藩や長州藩の人びとにとっては目の敵ともいえる人物です。そういう人物の屋敷だったところに、明治天皇に関連する施設をつくるということについて、薩摩や長州出身の人々が忌避感を覚えることはなかったのでしょうかね?
さて、500円を払って御苑北門から入り、森の中を歩いていきます。しばらく進むと下り坂となり、右側に建物が見えてきます。この建物は隔雲亭といって、1900年に明治天皇が昭憲皇太后のために建てた休憩所だったそうです。太平洋戦争中に戦災にあって焼失しましたが、戦後の1968年に再建されました。
隔雲亭から坂を下っていくと、目の前に広がるのが下の写真の南池です。森に囲まれた静かな池なのですが、ここって渋谷区ですからね。たくさんの人で賑わう渋谷区に、こんな自然豊かな場所があるなんて信じられない気もします。まさに都会の中のオアシスですね。昭憲皇太后もここで釣りを楽しんだそうで、池のほとりには御釣台と名付けられた、池にせり出したテラスのようなものも設けられていました。

南池を時計回りにぐるっと1周して、その先に進むと見えてくるのが菖蒲田です。時期的に菖蒲の見られる季節ではなかったのですが、花が咲く季節はさぞ美しいことでしょう。とりあえず今回はその風景を想像して楽しむことにしました。この菖蒲田も、明治天皇によって整備されたのだそうです。
〝うつせみの 代々木の里は しづかにて 都のほかの ここちこそすれ〟
この歌は、明治天皇がこの地で詠んだものです。「静かで都心とも思えない」というのは、この歌が実際に詠まれたころよりも、現在のほうがより相応しいのかもしれません。
菖蒲田を横に見ながら、さらに先へ進んでいきます。このあたりも木々が生い茂り、大都会にいることを忘れてしまいそうになります。左にある菖蒲田は少し低い位置にあり、右手にある森はやや高い位置にあります。地図で確認してみても、このあたりは細長い窪地のような地形になっていることがわかります。
しばらくすると道は突き当りとなり、左に下りていく階段が現れます。この階段を下りたところにあったのが、下の写真の井戸です。この井戸は〝清正井〟と呼ばれており、虎退治で知られる加藤清正が掘った井戸なのだそうです。江戸時代初期、この場所には加藤家の下屋敷がありました。そのことから、清正に関わる話が生まれたのでしょうが、清正自身がこの屋敷に住んだかどうかについては、はっきりとしたことはわかっていないようです。

考えてみれば、菖蒲田からこの井戸があるところにかけては窪地になっていて、窪地のいちばん奥まったところにこの井戸があるのですから、ここは水が湧く地形だといくことになります。清正が掘るまでもなく、ここには湧水があったのではないでしょうか。現在でも、毎分60リットルもの水が湧き出ているそうで、一年を通じて温度も15℃前後と安定しているようです。写真ではわかりにくいと思いますが、確かにきれいな水が滾々と湧き出ていました。ここはパワースポットしても有名で、休日などは多くの人が列を作っているそうなのですが、この日は2~3人の外国人がいただけで、特に並ぶこともなく近くまで行くことができました。
加藤家は、清正の子忠広のときに改易(領地を没収されること)されます。前述した通り、その後は井伊家の下屋敷となりました。井伊家は、代々江戸幕府での重職を担ってきた家柄ですから、ここは江戸時代の初めから終わりまでの長い間井伊家の土地だったはずです。先々代で、しかもその期間も短い加藤家の痕跡があるのに、井伊家の痕跡を見つけることができないのは少々不自然な気がします。明治神宮が整備された1920年といえば大正時代の後期ですが、政府の中枢にいた人々のなかには、未だに井伊直弼に対しての複雑な思いを持つ人もいたのかもしれないですね。
御苑の静謐さに癒された私は原宿駅へと歩を進めたのですが、駅に近づくにつれて人の数が多くなっていきます。そして、原宿駅の喧騒の中に入っていくのがなんとなく躊躇われ、もう少しだけ歩いて見ようと思ったのです。
最初の地図で見ていただいた通り、明治神宮は東西を谷に挟まれた台地です。東側には混雑しているはずの表参道や竹下通りがあるので、あえて西側の谷のほうに向かってみることにしました。代々木公園の中を抜けてしばらく北に進んだところに〝はるのおがわプレーパーク〟と書かれた公園がありました。調べてみたところ、ここは「子どもたちが自然の中で思いっきり遊べる」ことをテーマにした公園なのだそうです。ホームページを見ると、子どもたちが水に濡れたり泥で汚れたりするのを気にすることなく、楽しそうに遊んでいる写真が掲載されていました。私自身も幼いころ、泥んこ遊びで靴や服をドロドロにして帰宅して母を困らせた記憶があります。昔はそんなことができる場所が家の近所にたくさんあったんですよね。今の子どもたちはこういう場所がないと、泥んこ遊びも体験できないのでしょう。なんだかちょっと可哀そうな気もします。
そして、この公園の片隅にあったのが下の写真の石碑です。

♪春の小川は さらさら行くよ
♪岸のすみれや れんげの花に
♪すがたやさしく 色うつくしく
♪咲けよ咲けよと ささやきながら〟
今はどうか知りませんが、昔は小学校の音楽の教科書にも載っていたので、知っている人は多いでしょう。その昔、ここには河骨川という小川が流れていたそうです。この歌の作詞をしたのは高野辰之という人物で、この他にも『朧月夜』『故郷』『もみじ』などの、数々の有名な唱歌を作詞しています。どれも日本の素敵な風景が目に浮かぶような歌ばかりですよね。『春の小川』は、高野辰之がこの近くに住んでいるときによく河骨川のほとりを散策しており、その風景を描いたものなのだそうです。
現在、河骨川は暗渠となり、石碑のすぐ横には小田急線の線路があります。しばらくここにいたのですが、その間にも電車が轟音を立てて頻繁に通過していき、とてもこの歌詞のような風景が見られたとは信じられません。がんばって当時の様子を想像してみようとしたのですが、それはすぐに電車の音に邪魔されてしまいました。
想像するのはあきらめて、ふと思ったのは「この場所に広がっていたのは先ほど訪ねた明治神宮御苑のような風景だったのかもしれない」ということです。そう考えると、明治神宮の森や自然は改めて貴重なものに思え、これらを残してくれた古の人々は素晴らしい決断をしてくれたんだということを実感します。大都会東京に残る〝奇跡の森〟と言うべき風景が、これからもずっと守られていくことを願いたいですね。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。