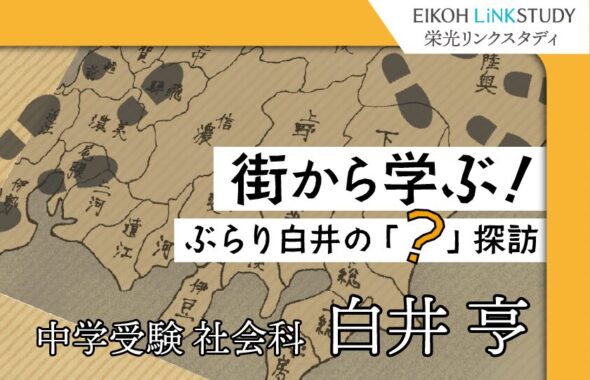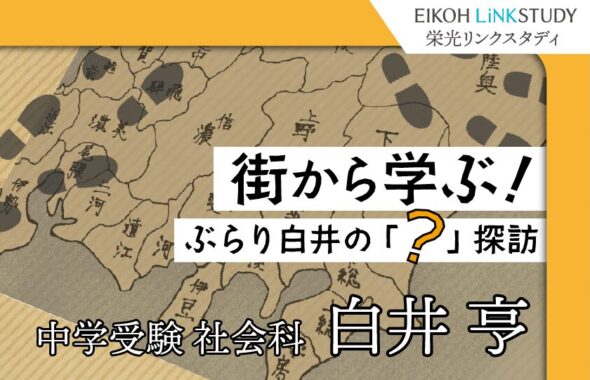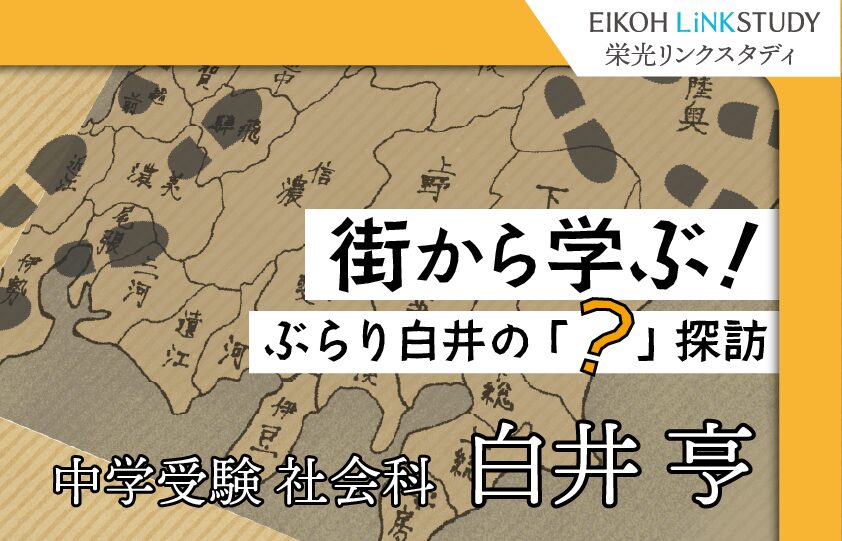
~東京都八王子市
移動した「桑都」編vol.1~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
東京都八王子市は人口約58万人、東京都では最も人口の多い市です。下の地図を見てもわかる通り市域も広く、東京都では奥多摩町に次いで2番目の広さです。インバウンドにも人気の観光地として知られる高尾山も八王子市内にあり、市の西側は山間部になっています。

新宿駅から中央特快で約40分、市の中心部にある八王子駅は、首都圏に降雪があると必ずと言っていいほどテレビの中継先となります。この駅ビルを背景に、雪の様子をレポートしているのを見たことがないでしょうか。気象庁のHPで確認してみたところ、1月の平均気温は東京都心と比べて2℃ほど低くなっているようですね。

千葉県民の私にとって八王子は、中央自動車道を通って山梨県方面に向かうときの1つの区切りとなっていたところです。行きは混雑する首都高を抜けて八王子まで来ると少しホッとし、帰りは坂やカーブの多い道を抜けて平坦な道になると一息ついたものです。
そして、その中央自動車道の渋滞ポイントになっていたのが〝元八王子バス停〟です。このあたりは下り坂と上り坂の境目の谷になっており、上りに差し掛かった多くの車が減速してしまうため渋滞が起こりやすいのだそうです。連休やお盆のときによく見る渋滞の映像も、たしかこの付近のライブカメラが使われていたはずです。
・・・と、ここで1つの疑問が湧いてきたのです。
「元八王子という地名があるということは、何らかの事情で八王子の街は移動したのではないだろうか?」
これまでほとんど気にしたことがなかった元八王子バス停の位置を地図で確かめてみたところ、やはり現在の八王子市街地よりかなり西にあることがわかりました。さらに、元八王子バス停よりも西には、元八王子町という住所があることもわかったのです。そして、その元八王子町のいちばん西にあるのが八王子城跡です。もしかすると、この城が八王子の始まりに何らかの関係があるのでは?…と考え、まずは城跡を訪ねてみることにしました。

八王子城跡の最寄り駅は、八王子駅ではなくその2つ先の高尾駅です。駅から城の入り口付近まではバスで向かうことができ、私も今回はこれを利用しました。ただし、このバスは土休日のみの運転なので、みなさんが訪れるときは注意してください。平日だと歩く距離が少し増えます。
八王子城が築城されたのは16世紀の終わりごろ、小田原城を本拠地とする北条氏の支城としてつくられました。その少し前に、武田信玄による小田原城攻めと三増峠の戦いが起こっていますので、この城は甲斐国方面の防御拠点として築かれたのでしょう。城が築かれた山はもともと深沢山とよばれていて、この山に八王子権現という神が祀られていたことから八王子城という名になったそうです。現在のこの山は、八王子城が築かれた山ということで城山と呼ばれています。

せっかく築いた八王子城ですが、残念なことに比較的短い期間で廃城になってしまいます。
1590年、豊臣秀吉は北条氏征伐のための戦いを起こします。その際に、この八王子城も戦いの舞台となりました。前田利家、上杉景勝、真田昌幸ら15000の軍に攻められた八王子城は、激戦の末多くの死者を出して落城します。北条氏も滅亡し、その後この地は徳川家康によって治められることになって、八王子城は廃城となるのです。
八王子城は山城ですので、城の中心となる本丸は城山の山頂付近にあります。本丸には、城の名の由来となった八王子権現が祀られている神社もあるのですが、そこまで行くのはかなりの山登りをしなければなりません。その後の歩きも予定していたので、今回は城主が居住していた御主殿跡まで行ってみることにしました。もちろんここまでもずっと上り坂ですよ。
上の写真の橋を渡った先の階段を上ったところにあるのが御主殿跡です。ここは発掘調査が進められているようで、建物の礎石や復元された屋敷の様子などを見ることができ、当時の姿を偲ぶことができました。
元八王子の名は、おそらく八王子城の城下町があったことで付けられたのでしょう。城内からは、東の方に向かって城山川という川が流れ出ています。川に沿いには緩やかに傾斜した平らな土地ができているので、家臣たちが住居を構えるのに都合がよかったと思われます。八王子城は短期間で廃城になってしまったので、商人などが住む本格的な城下町はできなかったかもしれませんが、元八王子町のあたりには家臣たちが暮らす城下町が形成されていたのでしょう。
そうすると、元八王子町の城山川沿いの地域に、何か城下町の痕跡が残っているのかもしれません。
それを探すべく八王子城を後にして、もともとここを訪れるきっかけにもなった中央道元八王子バス停を目指して歩き始めました。その道程のほとんどは、元八王子町を西から東へ横断していくルートになります。
八王子城の入り口から緩い坂を下っていくと、中央自動車が見えてきました。その下を通り抜けてしばらく進むと、宮の前という交差点に差し掛かりました。名前からするとこの近くには神社があるはずなので地図を確認したところ、八幡神社という名が目に留まりました。八幡といえば武運の神ですから、もしかすると八王子城と何か関係があるかもしれないと思い、八幡神社を目指してみることにしました。

もう間もなく神社に辿り着くというところに、大きな木の切り株がありました。調べてみたところ、この切株は〝梶原杉〟と名付けられており、1972年までは立派な杉の木があったのだそうです。残念ながら木が枯れてしまったため伐採されてしまったのですが、この木を植えたのは源頼朝に仕えた武将梶原景時なのだそうです。さらに、この地に八幡神社を建てたのも梶原景時で、残念ながら16世紀末にできた八王子城とは関係なさそうです。
ところで、梶原景時というと源平合戦の折に何かと源義経と対立したことで知られており、どちらかというと嫌われ者のように描かれることが多い人物です。判官びいきの言葉の通り、義経は人気の高い歴史上のヒーローの1人ですので、それと対立する景時はどうしても悪役になってしまうのですね。でも、義経と景時の対立する場面をよく読んでみると、必ずしも景時が悪いようには思えません。義経という人物は軍事の天才です。天才の考える作戦は、常識的な価値観を持つ景時には危険だと感じたのでしょう。歴史上よく知られる義経の戦い方は、成功したからこそ称賛されていますけど、見方を変えれば博打のようなものだったのかもしれません。もちろん、イチかバチかの大勝負をできるからこその天才なんですけど、常識的にものを考える景時からは危険なものに見えたのでしょうね。
話をもとに戻します。
八幡神社で参拝して、境内の裏手のほうから中央道に沿った道を歩きます。しばらく歩くとその道は途切れ、少し広い通りに出てまた中央道の下を通り抜けます。こういう道は歩きやすいですけど、歩いていてあまり楽しくはありません。そこで地図を確認したところ、先ほど八王子城で見た城山川沿いに遊歩道らしき道があるのを見つけました。前述した通り、この川は八王子城内を流れていた川で、先ほど訪ねた御主殿跡の近くには御主殿の滝という小さな滝がありました。御主殿の滝は、八王子城落城の際に死者の血で三日三晩真っ赤に染まったと言われていますが、そんなことはまったく感じられないのんびりした川沿いの道の散策を楽しみながら元八王子バス停に辿り着きました。

バス停に着いたということは、もうすでにここは元八王子町ではありません。残念ながら、ここまでに城下町の痕跡らしいものは見つけられませんでした。
さて、この後は「もう1つの八王子」へと進んでいくのですが、ちょっと長くなってきましたね。…ということでこの続きは次回のブログで!
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。