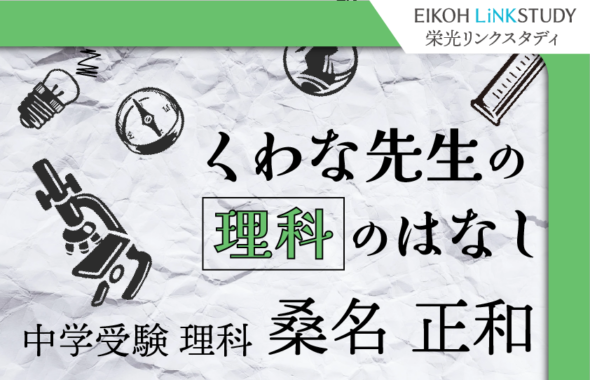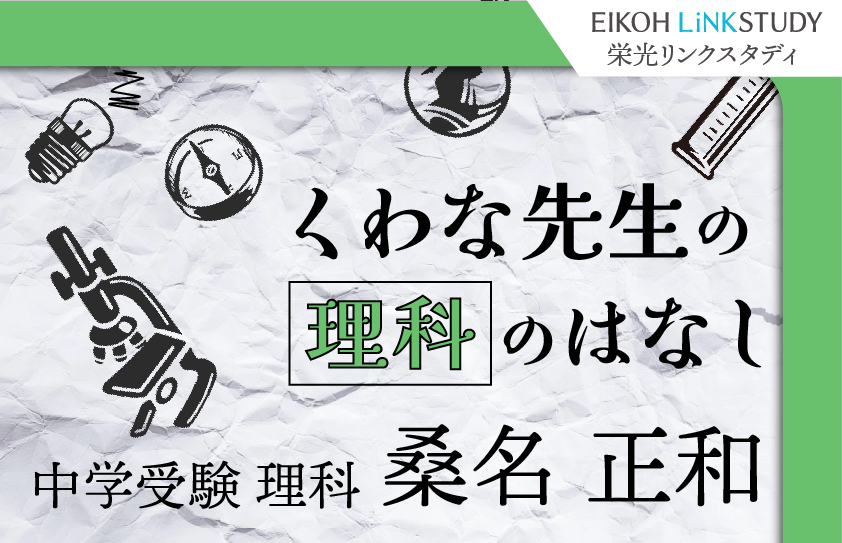
街路樹のツツジ
入学式シーズンはサクラが満開になり、レジャーシートを広げて花見をしている光景も多く見ました。
サクラの時期が盛り上がりを見せる分、サクラの時期を過ぎるといくらかさびしいものを感じます。
1か月後にはゴールデンウィークとなりますが、その時期の大通りの街路樹はピンク色に染まっています。

ピンク色がきれいなこの花はオオムラサキツツジ、街路樹を代表するツツジの1種です。
ツツジは中学受験理科でも登場する植物でツツジ科ツツジ属に分類されています。
ツツジは小学4年生で「春の植物」の1つとしても学習しますが、小学6年生で森林の植物について勉強するときに「低木」の1つとしても登場します。
低木は樹高が2~3m程度に成長する、樹木の中でも低い種類のものをさします。ツツジの他にアジサイやヤツデなども低木として学習します。道路わきにはえているオオムラサキツツジは低木の中でもやや低めで2mくらいまで成長します。それでも街路樹で2mもの高さになっているのを見ることはありませんが、歩道と車道が見渡せるように定期的に剪定されているからです。まったく手入れをしなければ、おそらく歩道から車道の様子がわからないくらいに大きく成長しているはずです。
街路樹ではオオムラサキツツジをよく見ますが、公園ではいろいろな色のツツジが咲いていました。

真っ白が特徴なものはリュウキュウツツジという種類のようです。
ツツジは横からみると、1本の長いめしべが上をむいていることがわかります。
めしべの先に花粉がつきやすいように上向きということです。

ツツジの上の花びらには濃い点々の模様が見えます。
「ガイドマーク(蜜標)」と呼ばれていて、みつがたくさんあるほと、色が濃くなります。
昆虫はガイドマークを見て、花の中にみつが多いことがわかり、花に近づいていきます。昆虫が到来したあとなど、花の中のみつが減るとガイドマークの色が薄くなっていきます。
さらにすごいことは、ツツジの花全体に太陽の光が当たったときに、ガイドマークの部分が紫外線で濃い色になり、紫外線を感じることができる昆虫が見たときに、蜜が多いことがはっきりとわかるそうです。ヒトの眼は紫外線を感じることができないので、昆虫の気持ちになりきることができないのが残念です。
道路わきによく見るツツジですが、ピンク色の花がきれいだという理由で植えられているわけでもないようです。交通量が多い都会の道路わきにはえている植物ですから、自動車の排気ガスが気になるところです。また、家で育てるわけではないので、毎日水をあげるというようなこともありません。そういう場所でも何年間も枯れることなく生え続けることができる植物としてツツジがふさわしいということになります。また、ツツジは根に共生する菌根菌(きんこんきん)という菌がいて、ツツジの根に栄養を効率よくわたしていることが知られています。マメ科の植物が根に菌を共生していることは高校生が学習する生物でもでてくるところですが、ツツジも似たような根での共生があります。
街中の景観を保つことが大きな目的で植えられている街路樹ですが、選ばれている植物の選定理由にはかなり奥深いようで、このあたり私もまだまだ知らないことがあるのではないかと思っています。

こちらのツツジは「サツキ」という種類です。
花の色はオオムラサキツツジに似ているのですが、花と葉はオオムラサキツツジよりもひとまわり小さめで、葉はややかためです。
5月のことを「さつき」といいますが、オオムラサキツツジよりも開花時期が遅く、5月になってから開花時期です。街路樹としてよりも、建造物にわきに植えられているのをよく見ます。
身近なだけに、あまり注目しないかもしれないサツキの紹介でした。