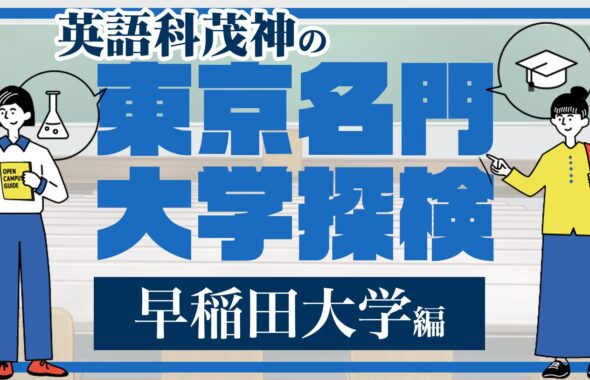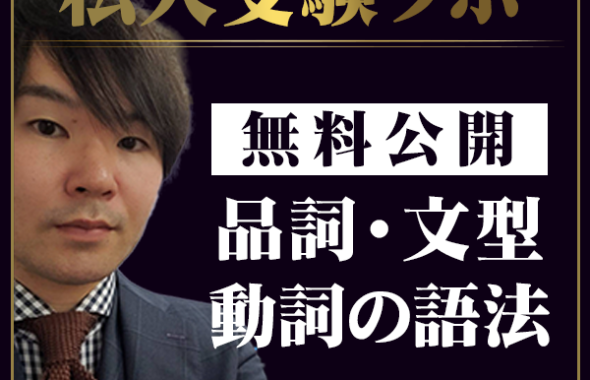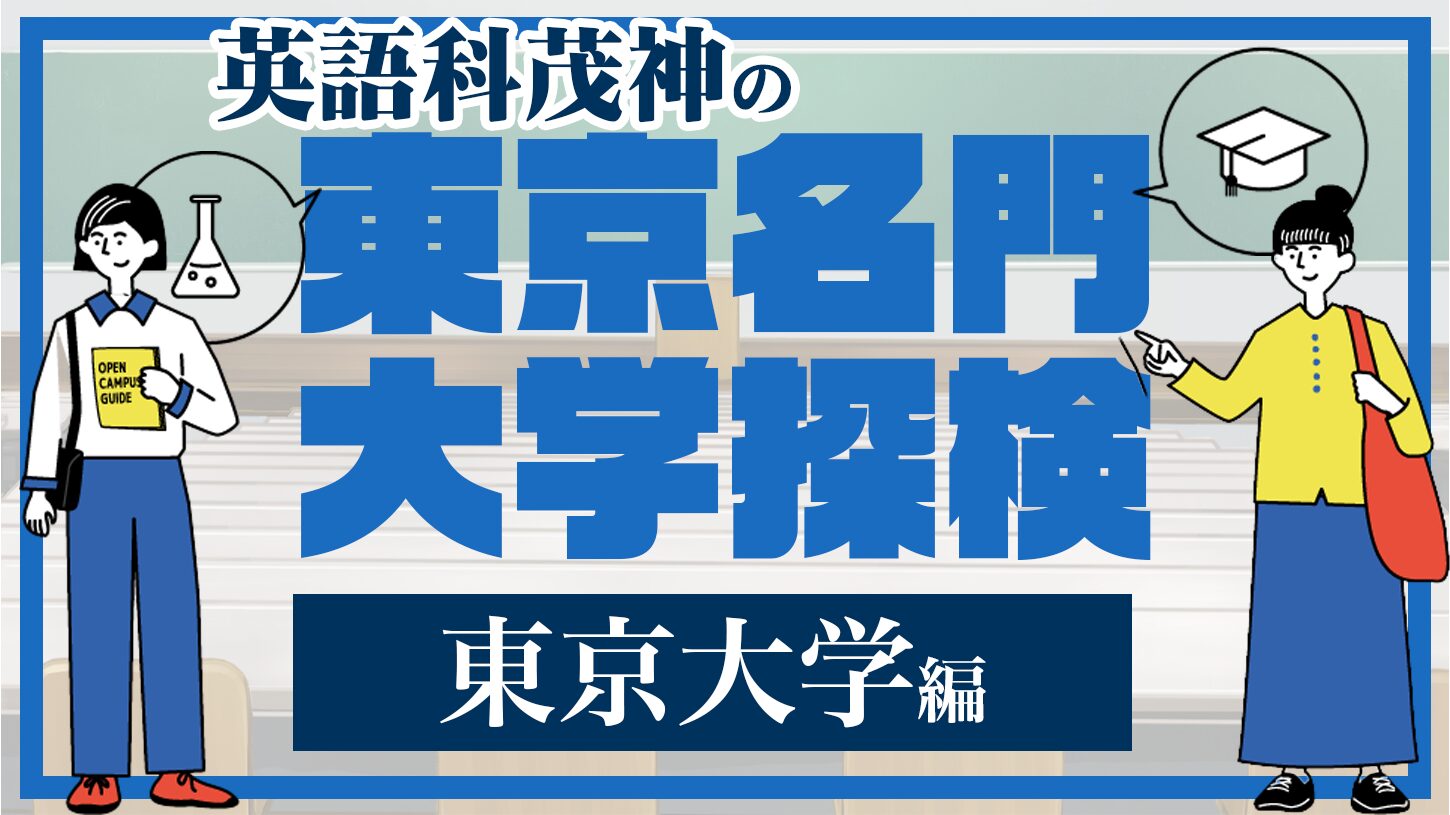
茂神の東京名門大学探検~東京大学編~
こんにちは、英語科の茂神(もがみ)です!
今回は日本の知の最高峰に君臨する「東京大学」本郷キャンパスをご紹介します!
以前からブログを見てくださっている方は、「あれ?早慶じゃなくて東大??」と思われる方もいるかもしれません。
、、、なんと!
リンスタでは2026年度より、従来の早慶などを対象とした難関私大コースに加え、旧帝大などを対象とした難関国公立コースを開講します。そのため、従来の私大に加え、今後は難関国公立に関する話題や過去問解説なども取り上げていきます。
時を超えた知の殿堂~本郷キャンパスの歴史と風格~
東京大学本郷キャンパスはリンスタ水道橋本部からも近く(歩いて20分くらい)、今回は茂神が散歩しながら写真を撮ってきました!
ここ実は江戸時代には加賀藩前田家の上屋敷があった場所であり、現在でも至る所に当時の面影を色濃く残す場所が存在します。また、戦時中もほとんど空襲の被害を受けることが無く(終戦後、GHQの司令部として接収する目的で意図的に標的を外したとの説あり)、当時の重厚な建築を随所に見ることができます。
最寄り駅は、東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線の「本郷三丁目駅」、南北線の「東大前駅」。飲食店や飲み屋が立ち並ぶ本郷三丁目の交差点を渡り少し進むと、右手には広大な大学のキャンパスが広がります。
都心にありながら一歩足を踏み入れると、そこは外界の喧騒が嘘のような、静かでアカデミックな空気に満ちています。歴史の重みを感じさせる重厚な建築物と、四季折々の表情を見せる豊かな自然が調和した空間は、まさに「知の殿堂」と呼ぶにふさわしい風格を漂わせています。
東大のシンボルを巡る~必見スポット5選~
1. 赤門(旧加賀屋敷御守殿門)
 東大と言えば、やはり赤門!本郷キャンパスの南西部に位置する門で、その鮮やかな朱塗りから広くこの名で親しまれています。正式名称は「旧加賀屋敷御守殿門」といい、国の重要文化財に指定されている東京大学のシンボル的存在です。
東大と言えば、やはり赤門!本郷キャンパスの南西部に位置する門で、その鮮やかな朱塗りから広くこの名で親しまれています。正式名称は「旧加賀屋敷御守殿門」といい、国の重要文化財に指定されている東京大学のシンボル的存在です。
この門は、江戸時代後期の文政10年(1827年)、加賀藩13代藩主前田斉泰が、11代将軍徳川家斉の娘である溶姫を正室として迎える際に建立されました。当時、三位以上の大名が将軍家から妻を迎える際には、朱塗りの「御守殿門」を建てるのが慣わしでした。建築様式は、本柱の背後に控え柱を立てた薬医門(やくいもん)で、屋根には優美な曲線を描く唐破風(からはふ)が設けられています。
 明治維新後、加賀藩邸跡地は東京大学の前身となる諸機関に利用され、赤門も大学の施設として受け継がれました。関東大震災や第二次世界大戦の戦火を免れ、現存する唯一の御守殿門として極めて高い歴史的価値を持っています。
明治維新後、加賀藩邸跡地は東京大学の前身となる諸機関に利用され、赤門も大学の施設として受け継がれました。関東大震災や第二次世界大戦の戦火を免れ、現存する唯一の御守殿門として極めて高い歴史的価値を持っています。
現在では、観光客が訪れる名所となっており、茂神が訪問した日曜日も、多くの外国人観光客で賑わっていました。
 ▲正門はコチラ。まっすぐ進むと安田講堂、右に曲がると総合図書館があります。
▲正門はコチラ。まっすぐ進むと安田講堂、右に曲がると総合図書館があります。
2. 安田講堂(東京大学大講堂)
 安田講堂は、赤門と並ぶ本郷キャンパスのアイコン的建造物です。正式名称を「東京大学大講堂」といい、国の登録有形文化財に指定されています。
安田講堂は、赤門と並ぶ本郷キャンパスのアイコン的建造物です。正式名称を「東京大学大講堂」といい、国の登録有形文化財に指定されています。
安田財閥の創始者である安田善次郎氏の寄付により建設が計画され、関東大震災後の1925年(大正14年)に竣工しました。設計は、当時の東京帝国大学総長で建築家の内田祥三が手がけました。
建物の頂上にある時計台が特徴的で、縦の線を強調した「内田ゴシック」と呼ばれる独自の建築様式で設計されています。これは、震災からの復興のシンボルとして、力強く天に向かって伸びるデザインが意図されたものです。講堂内部には約1,100席のホールがあり、地下には中央食堂が設けられています。
 また、安田講堂は日本の現代史における重要な出来事の舞台ともなりました。特に1968年から1969年にかけての大学紛争では、全共闘の学生らによって長期間占拠され、最終的に機動隊の突入により封鎖が解除された「東大安田講堂事件」は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。この事件により講堂は内部が大きく損傷しましたが、その後の修復を経て現在に至ります。
また、安田講堂は日本の現代史における重要な出来事の舞台ともなりました。特に1968年から1969年にかけての大学紛争では、全共闘の学生らによって長期間占拠され、最終的に機動隊の突入により封鎖が解除された「東大安田講堂事件」は、当時の社会に大きな衝撃を与えました。この事件により講堂は内部が大きく損傷しましたが、その後の修復を経て現在に至ります。
今日、安田講堂は東京大学の入学式や卒業式といった重要な式典の会場として使用されています。また、学術的な講演会やシンポジウム、音楽会なども開催され、大学の知と文化の中心としての役割を担い続けています。大規模な耐震改修工事も行われ、歴史的価値を保ちながら安全に利用できるようになっています。
 ▲地下には食堂や生協のショップが入っています。
▲地下には食堂や生協のショップが入っています。
3. 東京大学総合図書館
 東京大学総合図書館は本郷キャンパスの中心に位置し、安田講堂と並ぶ東大のランドマークです。東京大学附属図書館システムの中核を担い、約135万冊の蔵書を誇ります。
東京大学総合図書館は本郷キャンパスの中心に位置し、安田講堂と並ぶ東大のランドマークです。東京大学附属図書館システムの中核を担い、約135万冊の蔵書を誇ります。
現在の建物は、1923年(大正12年)の関東大震災で旧図書館が焼失した後、ジョン・ロックフェラーJr. から400万円の寄付を受けて1928年(昭和3年)に再建されたものです。設計は安田講堂と同じく内田祥三が担当し、共通のデザイン思想「内田ゴシック」様式で建てられました。建物の前にある噴水は、火災時の延焼を防ぐための防火水槽として、寄付者の要望で設置されたという歴史があります。
蔵書には、紀州徳川家伝来の「南葵文庫」や、文豪森鷗外の旧蔵書「鴎外文庫」など、国内外の貴重なコレクションが数多く含まれています。
近年、大規模な改修が行われ、歴史的価値のある本館の景観を保存しつつ、地下には300万冊を収蔵可能な自動化書庫や、学生が主体的に学べる「ライブラリープラザ」といった新しい空間が整備されました。伝統と最新の機能が融合した総合図書館は、東京大学の教育・研究活動を支える重要な役割を果たし続けています。
4. 三四郎池
 本郷キャンパスの中央部に深い森に囲まれて静かに水をたたえる「三四郎池」。この名称は、夏目漱石の小説「三四郎」で、主人公の三四郎と美禰子が出会う象徴的な場所として描かれたことに由来する通称です。
本郷キャンパスの中央部に深い森に囲まれて静かに水をたたえる「三四郎池」。この名称は、夏目漱石の小説「三四郎」で、主人公の三四郎と美禰子が出会う象徴的な場所として描かれたことに由来する通称です。
この池の正式名称は「育徳園心字池」。その歴史は江戸時代に遡り、もともとは加賀藩前田家の上屋敷にあった壮大な大名庭園「育徳園」の一部でした。造成は三代藩主・前田利常が、将軍・徳川家光の訪問に備えて行ったのが始まりとされ、その後も整備が重ねられ、江戸第一の名園と称されました。池の形が草書体の「心」の字をかたどっていることから「心字池」と呼ばれています。
明治維新後、加賀藩邸跡地が東京大学の敷地となり、この庭園も大学に引き継がれました。現在、池の周囲には鬱蒼とした木々が生い茂り、散策路が整備されています。都心とは思えないほど静かで自然豊かな空間は、学生や教職員にとっても貴重な憩いの場となっています。
5. 銀杏並木
 正門から安田講堂へと続く銀杏並木は、紅葉シーズンには圧巻の美しさを魅せてくれます。11月下旬~12月になると、辺り一面が黄金色の絨毯で敷き詰められ、幻想的な風景が広がります。
正門から安田講堂へと続く銀杏並木は、紅葉シーズンには圧巻の美しさを魅せてくれます。11月下旬~12月になると、辺り一面が黄金色の絨毯で敷き詰められ、幻想的な風景が広がります。
この道を歩きながら、ノーベル賞を受賞した偉大な先輩方も、同じように学問の道を志し、未来を夢見ていたのかもしれません。皆さんも、この並木道を歩きながら、自分の夢や目標について思いを馳せる日が来るはずです。高3の11月、受験勉強に疲れたその時、是非一度足を運んでモチベーションを高めてみては如何でしょうか。

東大大学院出身の篠崎先生(現代文・小論文)
高3現代文・小論文を担当する篠崎宏則先生は東京大学大学院出身。小論文個別添削や総合型選抜・推薦対策もお任せください!もし入塾されたら、キャンパスの魅力や大学周辺のおいしいお店など是非聞いてみてください!



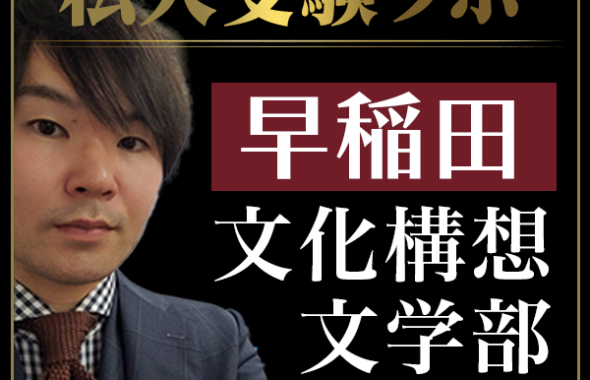
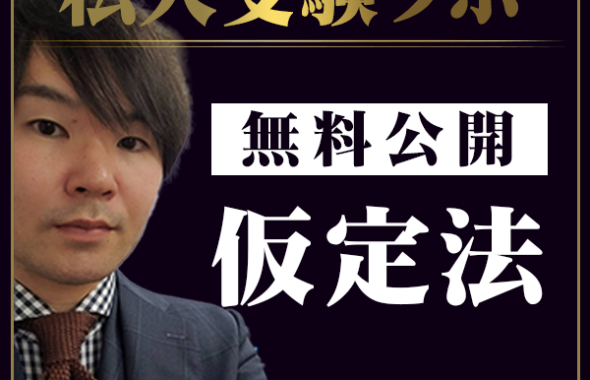
-590x380.png)