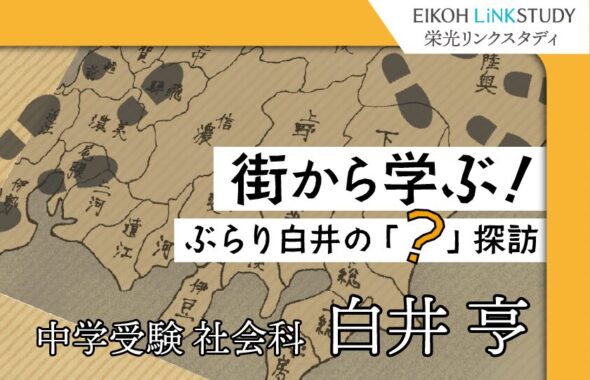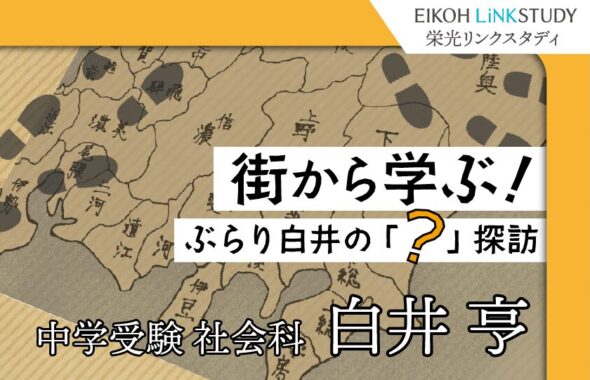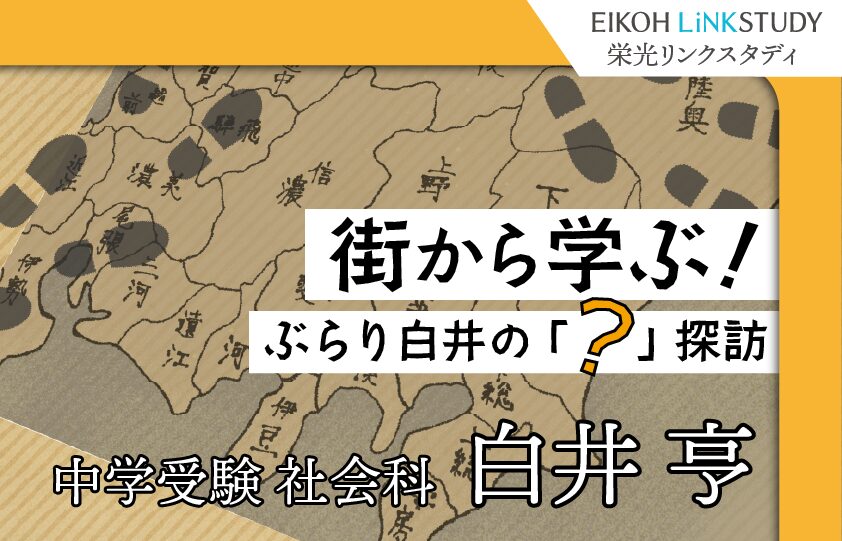
~三重県松阪市
牛肉の街のそれ以前編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
松阪市は、三重県中部、志摩半島の付け根あたりに位置する人口約150000人の都市です。県庁所在地の津市からJR紀勢線の快速電車か近鉄名古屋線の急行電車に乗ると、25分ほどで松阪駅に到着します。

さて、松阪という地名から多くの人が連想するのは、数あるブランド牛のなかでも特によく知られている〝松阪牛〟でしょう。「そうそう〝まつざかぎゅう〟だよね~」と言った人、実はそれ違うんですよ。松阪牛の正式な名称は「まつさかうし」です。もちろん、松阪に行って「まつざかぎゅう」と言ったところで、間違いを厳しく指摘されたりすることはありませんが、少なくとも地名は間違えないであげてほしいものです。
日本人が牛肉を食べるようになったのは明治時代のことです。もちろん、松阪牛もそれ以降ということになりますよね。調べてみたところ、江戸時代以前の松阪では、他の地域と同様に農作業や荷物の運搬に牛を使っていました。
明治の文明開化によって牛肉を食べる文化が日本に伝わると、東京や横浜には牛肉を食べさせる店ができました。それに目を付けた、玉城町(松阪市の南東にある町)出身の山路徳三郎は、松阪の牛を東京まで売りに行きました。当時はまだ鉄道もありませんでしたので、なんと3週間もかけて徒歩で牛を運びました。その苦労のかいもあって、松阪の牛はおいしいと評判になり、これをきっかけに松阪牛が広く知られるようになりました。

今回、松阪市を訪ねたのはおいしい牛肉を食べるためではなく、松阪が牛肉の街になる〝それ以前〟が気になったからです。…ということで、早速街に出てみることにしましょう。
リンスタのテキストには、松阪出身の人物が2名登場しています。
1人目の人物はこのように紹介されています。
「産業の発達にともない,都市部を中心に商業が発達しました。江戸では,三井高利によって越後屋という呉服店がつくられ,繁盛しました。この越後屋は,現在の三越百貨店のもととなっています。」
三井高利は、1622年に松阪の商人の家の末っ子として誕生しました。52歳のときに、江戸の日本橋に「三井越後屋呉服店」を開き、それまでにはなかった新しい商売の方法を採用しました。それが、「店前売り」と「現金掛値なし」です。当時の商売は、商人が得意先を回って注文を聞いて後から品物を届けたり、品物を得意先に持参して売ったりという、現在の訪問販売のような形が普通でした。また、代金の支払いについても、盆と暮れに利子を上乗せした金額をまとめて徴収するという形でした。高利はこのような方法を廃止し、店頭に商品を並べて、その場で現金を支払って買ってもらうというやり方にしたのです。以前のやり方は、購入できる人が限られ、しかも利子の分だけ価格が高くなってしまうという欠点がありました。高利の新しい商法は、誰もが気軽に、求めやすい価格で購入できるというメリットがありました。
また、高利は物を販売することだけでなく、こんなアイデアを実行しました。越後屋の店頭には雨傘が備えられていて、急に雨が降り出した時には自由に使うことができたそうです。この傘には大きな文字で「越後屋」と書かれており、傘をさして歩く人によって自然に越後屋の名が宣伝されるという、いわばコマーシャルということですよね。 このような商売の方法は江戸の庶民に広く受け入れられ、三井越後屋呉服店はとても繁盛しました。これが後の三越百貨店や三井財閥へとつながっていくのです。
松阪駅から駅前の通りを進み、右に曲がってしばらく歩いたところには、下の写真のライオンの像があります。このライオン像、どこかで見たことありませんか? みなさんのなかには、日本橋や銀座の三越百貨店に行ったことがある人もいるでしょう。その入り口にライオン像が置かれているのを見たことがないですか? 日本橋の三越本店では玄関の両脇にある2体のライオン像が出迎えてくれますよね。2体のライオン像は、日本橋三越開業時の1914年から鎮座しているそうですが、松阪市のライオン像は、2016年に三井家と松阪市の歴史と未来をつなぐ象徴として三越百貨店から寄贈されました。この像に跨ると願いが叶うということなのですが、さすがそれは実行できませんでした(笑)

そして、ライオン像の目と鼻の先にあるのが、下の写真の「三井家発祥の地」です。写真でもわかるように、門の前には柵が置かれており、中に入ることはできませんでした。この門の奥には、三井高利の産湯に使ったという井戸が残されているそうです。もちろん、当時の屋敷はもっと広かったはずで、このあたり一帯が三井家の敷地だったんでしょうね。

三井家発祥の地は、江戸時代に伊勢神宮に向かう数多くの人々が行き交った伊勢街道に面しています。この道を100mほど北に進んだところには、下の写真の建物がありました。

この建物は「旧小津清左衛門家」で、昔の商人の屋敷跡です。小津家は紙を扱う商人で、江戸でも一番の紙問屋として繁盛していました。小津家も、三井家と並ぶ松阪屈指の豪商でした。屋敷の中を見学することもでき、かつての繁栄の様子を目にすることができます。とても広い屋敷なのですが、現在の屋敷は当時の敷地の約5分の3に過ぎないんだそうです。
リンスタのテキストに載っている2人目は、この小津家出身の人物です。
2人目の人物はこのように紹介されています。
「仏教が伝わる以前の日本人の考え方を研究する国学は,『古事記伝』を著した本居宣長によって大成されました。」
国学というのは、江戸時代を代表する学問の1つで、日本の古典を研究することで、外国の文化に影響されない、日本の本来の姿を探求する学問のことです。本居宣長は、代表的な国学者としてテキストに載っているわけですね。本居宣長の邸宅があった場所は「本居宣長旧宅跡地」として残されており、この場所で宣長は国学の研究に勤しんだのだそうです。下の写真を見てわかるように、敷地内には特に何も残されていません。というのは、ここにあった建物は松坂城内に移築されて保存されているからです。そこには本居宣長の記念館もあるのですが、残念ながらこの日は休館日でした。旧宅跡は小津家や三井家のあった伊勢街道の1本西側の道沿いにあります。この道沿いには、松阪牛の名店として知られる牛銀があり、店の外には行列もできていました。
宣長が大成した国学は、幕末の尊王攘夷思想に影響を与え、それが江戸から明治へと時代を動かしていくわけですね。そう考えると、松阪は日本の近代化に大きく貢献した街だということもできるかもしれませんね。

ところで、松阪市のHPにも「豪商のまち松阪」という表記があるのですが、なぜ松阪には大商人が多く生まれたんでしょうかね?
もちろん、三井高利のように商売上手な商人が多かったこともその理由でしょう。伊勢木綿のように松阪ならではの特産品があったということもあります。でも、それだけならば他の地域にもあったはずですよね。やはり、松阪の商人を支える大きな力があったのではないかと思うのです。
ということで、次に向かったのは松坂城跡です。
松阪城を築いたのは、信長や秀吉に仕えた武将である蒲生氏郷です。氏郷はもともと近江国(現在の滋賀県)に領地を持っていましたが、秀吉の命令によってこの地にやって来ます。その際に、近江の商人たちを連れてきて城下町に住まわせ、松阪の商業が発展する基礎を作ります。
城内に足を踏み入れてまず目を見張るのが、高く聳え立つ石垣です。下の写真でもわかるように、これだけ立派な石垣がある城はそう多くはないでしょう。残念ながら、城内に当時の建物は残されていませんが、この石垣だけでも見ごたえのあるものでした。 本丸跡まで登って行ったのですが、その道のりはなかなか複雑でした。松阪城を攻める敵は何度も方向を変えながら進んでいかなくてはならないはずで、この城を攻め落とすのはおそらく困難だっただろうということが想像できます。

江戸時代になると、松阪は紀州藩の領地となります。
紀州藩といえば、徳川御三家の1つに数えられる藩で、江戸幕府の8代将軍徳川吉宗が紀州藩の出身であることはよく知られていることです。紀州藩は徳川御三家という格式の高い家柄ですから、おそらく出費も多かったはずです。江戸時代の大名というのは、その多くがお金に困っていました。そんな大名たちが頼りにしたのが、お金を持っている商人たちでした。松阪の商人たちも、紀州藩と大きなつながりがあったのではないかと思います。紀州藩としては、松阪の商人が大きな利益を上げてくれたほうが都合が良いわけですよね。そう考えれば、紀州藩が松阪商人たちのためにいろいろと便宜を図ったということは想像に難くありません。先ほど、三井家の越後屋呉服店は日本橋にあったと書きましたが、当時の日本橋は江戸の経済の中心地でした。そんな一等地に出店できたというのも、紀州藩の後ろ盾があったからなのではないかと思うのです。おそらく、他の松阪商人も便利な場所に出店できたのではないでしょうかね。そして、松阪には多くの豪商が生まれ、その利益の一部が紀州藩の財政を潤すという、いわばWin-Winの関係だったということです。
松阪城の南側には、下の写真の御城番屋敷があります。 石畳の道と緑の生け垣が印象的なこの通りには、松坂城を警護する武士20人とその家族が住んでいました。驚くのは、現在でもその子孫の方々がここで生活しており、屋敷の維持や管理をしているということです。古い家屋を残すのはとても大変なことで、ましてやそこで生活をするにはかなりのご苦労があるのではないかと思うのです。それでも、このような貴重なものを残してくれているということには、大いに感謝をしなければいけないでしょう。生垣の間から武士が出てきてもまったく違和感のない道をしばらく楽しんだ後は、松阪駅へと向かうことにしました。

御城番屋敷から15分ほど歩いて戻ってきた松阪駅前には、下の写真のようなモニュメントが置かれています。
松阪に着いたときにはなぜが目に入らなかったのですが、実は同じものを他の場所で見ていたことを思い出しました。その場所というのが、松阪城の近くにあった〝本居宣長ノ宮〟で、駅前のよりも小さなサイズのものが社殿の近くに置かれていました。…ということは、これは本居宣長に関係するものということですね。

調べてみたところ、これは〝驛鈴〟というもので、写真の驛鈴の真ん中あたりにも「驛」の文字が確認できます。奈良時代から平安時代にかけての頃、公務で旅をする役人は馬を使って移動することが許可されていました。驛鈴は、馬を使用できる許可証のようなものだったそうです。
本居宣長は、自分の書斎にも鈴をかけ〝鈴屋〟と名付けていたくらい、鈴がとても好きだったのだそうです。宣長は研究者ですから、長い時間机に向かって書物を読んだり、本の執筆をしていたりしたことでしょう。そんな宣長をリラックスさせてくれたのが鈴の音だったのかもしれませんね。
松阪散策を終えた私も、歩き疲れた足をリラックスさせるため、近鉄線の特急電車の座席にゆったりと座りながら松阪の街を離れることにしました。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。