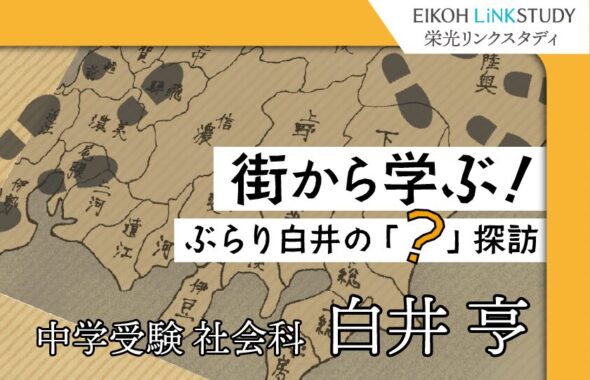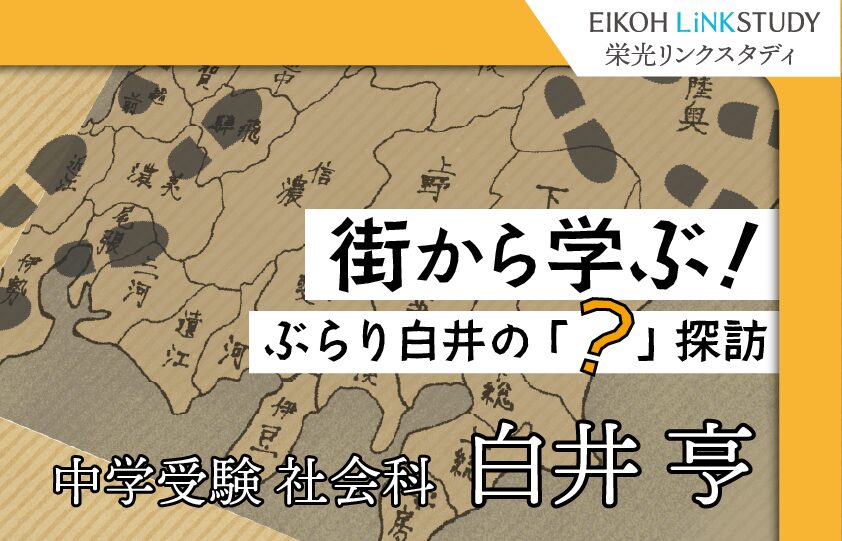
~山梨県甲州市
古刹と不思議な山編~
みなさんこんにちは。
リンスタ社会科担当の白井です。
山梨県大月市と甲州市の境にある標高1096mの笹子峠は、甲州街道随一の難所として知られていました。峠にあった茶屋では、疲れた旅人をもてなすための餅が売られていたそうです。大月市側にある笹子駅の近くには、今でのその流れをくむ「笹子餅」という餡入りの餅を製造するお店があります。かつては、中央線の車内でも笹子餅を売りに来ていたものですが、今ではこのお店とすぐ近くにある酒造でしか買えなくなってしまいました。私も車内販売があったころに購入したことがあったのですが、粒餡をくるんだ蓬入りの餅がとても美味しかったことを覚えています。なかなか買うことができないのはちょっと寂しい気もしますね。
笹子峠を貫く長いトンネルを出た中央本線の電車は、甲府盆地へと坂を下って行きます。この区間の車窓はとても素晴らしく、勝沼ぶどう郷駅のあたりからは眼下に甲府盆地の大パノラマが広がり、晴れていればその背後には南アルプスの美しい山々を見渡すことができます。昼間だけでなく、甲府盆地の夜景を見下ろせる夜の車窓も見応えがあります。
しばらく下って行くと、下の写真のような山が見えてきます。写真からも背後に連なる山よりも少し手前にあることがわかると思います。山の手前に町がありますが、背後にも街並みは続いているようですね。…ということは、山の周囲は平地に囲まれていて、ここだけが高くなっているってことでしょうか。「もしかしたら人工的につくられた山かも!」…って思う人がいてもおかしくないような風景です。

この山を地図で確かめてみましょう。やはり思った通りで、周囲の山々からは独立した存在であることがわかりますよね。なぜここだけが山になっているんでしょう??
この山の名は「塩ノ山」といい、甲州市のホームページには次のようなことが書いてありました。
『その昔、デーラボッチという大力坊が芋殻の棒で二つの山を担いできた。棒が折れて落ちた山の一つが塩ノ山になった』
…昔から伝わる伝説に敬意を表して、「もう1つの山はどこに行ったんだ?」というツッコミを入れるのはやめておくことにしましょう(笑)
中央本線の電車に乗るたびに、いつも気になっていた山なのですが、今回はこの山に登ってみようと思い立ったのです。

塩ノ山の最寄り駅は塩山駅です。現在は市町村合併によって甲州市となっていますが、かつては塩山市という市がありました。もちろん、その名の由来は「塩ノ山」です。このような名がついていることから、昔はこの山から岩塩でもとれたのかと思ってしまいますよね。調べてみたところ、地名の由来は塩とはまったく関係ありませんでした。平地のなかに独立した山である塩ノ山は、まわりのどこからでも見ることができます。つまり「四方から見える山」ということですよね。これが「しほうのやま」となり、「塩ノ山」となったのだそうです。
塩山駅に着いてここで昼ご飯を食べようと駅の外に出たところ、数分後に恵林寺に行くバスが来ることがわかりました。恵林寺は武田信玄の菩提寺として知られており、観光地にもなっています。観光地ならば飲食店もあるだろうと思い、やって来たバスに乗り込んで恵林寺に向かうことにしました。15分ほどで最寄りのバス停に着き、まずは参拝をすることにします。

応仁の乱によって荒廃していた恵林寺は、戦国時代に武田信玄によって再興されます。信玄によって京都から高僧が招かれますが、その中の1人に快川紹喜という僧がいました。信玄がなくなった後、あとつぎの勝頼によって執り行われた葬儀の際には、快川が導師を務めました。導師とは、葬儀において中心的な役割を担う僧のことです。
勝頼の代で武田氏は滅亡します。甲斐国に攻め込んできた織田軍は、恵林寺に逃げ込んでいた武士の引き渡しを要求しますが、快川はこれを拒否します。恵林寺は織田軍によって焼き討ちにあい、多くの僧とともに快川も山門の上で焼死してしまいます。燃えさかる炎の中で、快川は「心頭滅却すれば火もまた涼し」と唱えたと伝えられています。これは「心の中の雑念を打ち払ったならば、たとえ火の中にいようとも涼しく感じる。」「いかなる苦痛も心の持ち方しだいで、しのぐことができる。」という意味で、恵林寺の三門にはこの言葉が掲げられています。

立派な本堂や枯山水の庭園、うぐいす張りの廊下、明かりのない空間を手探りで進む冥歩禅、本堂の裏にある庭園(上の写真)などをゆっくりと堪能しました。特に、信玄の姿を模して造られたという武田不動尊からは何とも言えない威厳を感じられ、しばらく時間を忘れてその前に佇んでしまいました。
残念ながら、武田信玄の墓所は月命日の12日のみの公開でみることができなかったのですが、江戸幕府の5代将軍徳川綱吉の側用人として幕政を主導した柳沢吉保の墓所と木像を見ることができました。吉保は武田信玄を崇拝していて、甲府藩主だったときには恵林寺で信玄の百三十三回忌法要をおこなっています。
さて、この後はバスで戻って塩ノ山に登ろうとバス停まで来たのですが、なんと次のバスは約1時間後! そうなんです。先ほど塩山駅ですぐにバスが来たため、帰りのことはまったく考えておらず、バスの時間を確かめるのを完全に忘れていました。ここから、塩ノ山への登り口がある向嶽寺までは約2㎞、歩けば30分程度でしょう。緩い下り坂となっているルートは、快適に歩けるはずです。…ということで、迷わず歩きを選択した私は、バス通りから1本離れた道を南へ向かって歩き始めたのです。下の写真のような、ぶどう畑と富士山という、いかにも山梨県らしい風景の田舎道を爽快な気分で歩いて行ったのです。

半分くらい歩いたでしょうか。ふと思い出したのがお昼ご飯のこと。そういえば恵林寺の近くで食べようと思っていたのに、バスのことですっかり忘れていたのです。そこで、せっかくなのでピクニック気分で山に登って食べようと、途中にあったコンビニでおにぎりを買って行くことにしました。
予想通り、30分程度で向嶽寺に到着しました。向嶽寺は600年以上の歴史がある寺院で、境内の建物も立派で、中には貴重な文化財や庭園もあるのですが、残念ながらこの寺院は一般には公開されていません。とりあえず挨拶がわりに本堂に向かって一礼して、塩ノ山への登り口を探すことにしました。
向嶽寺の境内は思いのほか広く、しばらく登り口を探してウロウロしてしまいました。ようやく「塩ノ山遊歩道」と書いてある看板を見つけ、いよいよ山登り開始です。
しばらくの間は、木々の間を気持ちよく進んでいったのですが、少しずつ足に疲れがたまってきました。途中からは、下の写真のような階段になっているところがあります。しっかりと登山道が整備されていているんだなと思うかもしれませんが、実はとても歩きにくいのです。木で作られた階段がつくられているように見えると思いますが、この木と木の間の土がかなりなくなってしまっており、この木がちょっとしたハードルみたいになっているんです。たぶん歩きにくいと思った人が多いんでしょう。階段の右側に、人が歩いたことでできたような細い道がありますよね。私もこの細い道を歩いていきました。

途中の休憩所でしばらく息を整え、また山道を進んでいきます。風はとても爽やかなのですが、途中から汗が止まらなくなってきました。念のためタオルを持ってきてよかったですが、ハンカチだけだったら困ったことになっていたかもしれません。2つ目の休憩所では、先ほどよりも少し長い休憩をとることにしました。汗を拭いて水を飲み、疲れた足を休めながら風に吹かれ、また山道に挑んでいきます。
ここからは山頂まで一気に登って行きます。途中で足が上がらなくなってきましたが、ここまで来た以上引き返すという選択肢はありません。再び汗を流しながらようやく辿り着いた山頂では、下の写真のような見事な景色が迎えてくれたのでした。


南の方角には富士山、その右側には甲府盆地とその背後にある南アルプスの山々、この見事な風景を見た瞬間に、山登りの苦労は完全に吹き飛んでいきました。そして、この風景を見ながらいただいたコンビニおにぎりは、それはもう格別の味だったのです。
ところで、この塩ノ山の上空ではUFOが多数目撃されているのだそうです🛸
下の地図でもわかるように、塩ノ山は富士山の真北に位置しています。これは偶然ではなくこの山はピラミッドであるという噂があるのだそうです。そして、そのピラミッドを目印にしてUFOが数多く飛来するのだとか…。また、この近くには「飛大(とびのみや)神社」という神社があります。この神社の名には、飛来してきたUFOを神として祀っているという意味があるのだとか…。さらに塩ノ山を上空から見ると勾玉の形をしているのだとか…。「信じるか信じないかは」 …やめておきましょう(笑)

UFOやピラミッドはともかくとして、山頂から真南の方角に富士山がきれいに見えたことは事実です。きっと昔の人々もこの山に登って富士山を見ていたのでしょう。富士山は信仰の山でもありますから、ここから祈りを捧げていたのかもしれませんね。
「?」はきっとそこにある
「?」を知ればおもしろい!
みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。